「センスがいい」とは「リズム(反復と差異)が面白い」こと。

今回は「センスの哲学」という本を読んで、自分に引き寄せて考えたことを備忘録的に書いておきたいと思います。
著者は千葉雅也さん。
現代思想入門、勉強の哲学などで知っている人も多いかと思います。
この本を購入してからしばらくの間、積読状態だったのですが、私が所属するタスクシュート協会の方々が「めっちゃよかった!」というので遅ればせながら最近読み終えました。
結論、めっちゃよかったです。
センスという抽象的な概念がタンジブルになってきた気がします。
めっちゃよかったのでこの本で読書会もやりました。
ここから先はセンスの哲学の中で個人的に魅力を感じた箇所を示しつつ、自分に引き寄せて考えたことを残しておきます。
遡ること2020年8月に、
センスは「知識」によってつくられ、あらゆる「選択」に発露する
といった主張の記事を書いたのですが、この主張の解像度がさらにアップした感じもしています。
めちゃくちゃネタバレするような内容ではありませんが、ネタバレ厳禁な方は本書を読んだ後にご覧ください。
センスとは何なのか?
まず、センスとは何なのか?という話。
この本でいう理論は「物事のそのものを把握する」のがセンスです。
そのものとは「リズム」のこと。
つまり、ものごとをリズムとして捉える=センスとなります。
そして、センスにおいて大事なことは、ものごとを意味的や目的的に捉えるのではなく、凸凹のリズムの問題として、どう並べているかで捉える。
凸凹のリズムを楽しむことが大事ということでした。
リズムとは、まず「形」のこと。
さらに、広い意味で、形、色、響き、味、触った感じなどをすべて「リズム=形」だと見なすことができると考えつという教えです。
そしてリズム=形には、
(1) 一定の反復があり、(2) そこから外れるとき=差異がある。
これがリズムの構造。
ここまでをまとめると、リズム=形には「反復と差異または規則と逸脱」があるということです。
それが物事のそのものであり、それを把握するのがセンスであると私は理解しました。
センスがいいとは何か?
では次に「センスがいいとは何か?」について。
これ、多くの方が気になる問いだと思います。
結論、この本によれば、センスがいいとは「面白いリズム(反復と差異)を作り出せること」です。
いかがでしょうか?
このような考え方を得た時、「〜センス」と付くものは私の中でほぼほぼしっくりくる説明がつくと感じました。
例えば、ファッションセンス。
例えば、パスセンス。
例えば、デザインセンス。
例えば、文章センス。
いずれにしてもセンスがいい、センスがあるとなる場合はそこに「面白いリズム(反復と差異)」がある。
そして、自分の経験に引き寄せた時に、一番ピンときたのは「ネーミングセンス」でした。
ネーミングセンスを感じるネーミング
例えば、音楽アーティストの「GReeeeN」。
これはみんなが知っているgreenという単語からの差異・逸脱。
そして「e」が4つ連なることも差異・逸脱であり、反復でもあります。
メンバーが四人いるからeが4つ並んでいるそうです。
文字の配列から面白いリズムを感じます。
初見でネーミングセンスがある、と思いました。
*
他には、標津(しべつ)小学校という北海道の小学校の運動会で行われている「サケとホタテをつんでミルク」というネーミング。
特産品である、鮭、帆立、牛乳の模造品を台に乗せて運ぶレースなのですが、配列が大変面白いネーミングで、見たこともない点で差異・逸脱してます。
カタカナが名前の中に定期的に現れる部分が「反復」になっているという分析を個人的にはしています。
こちも大変面白いリズムで、センスがいいと感じました。
*
それから「ダースベイダー」。
今やおなじみで説明不要となったこの名前も、差異・逸脱、反復が絶妙に組み込まれていると思います。
「Dark Father(暗黒の父)」をもじったものだと言われており、これが差異・逸脱ですね。
(ベイダーはオランダ語で父親という意)
そして、濁音と長音が繰り返し現れる点が「反復」です。
これの配列が絶妙で、非常に面白いリズムになっているのかなと。
だいぶ前に以下のポストをしたことがありましたが、ここに今回の話も加わり、だから脳裏について死ぬまで忘れない名前になっているのだろうなと強い確信を得ました。
1.日本人は「濁音と長音を組み合わせた音」を好む
— 田中 新吾 (@tanashin115) July 24, 2020
→バザールでござーる、グロービス
2.「濁音」は男たちを興奮させる
→ゴジラ、ガンダム、デビルマン
ネーミング的にも「ダースベイダー」が強い理由は「1+2」だから。
ジョージ・ルーカスは天才。
脳裏に焼きついて死ぬまで忘れない名前。
ジョージルーカスはネーミングセンス的にも天才だと思いました。
今回書いておきたかったことは以上になります。
あくまでも私の視点で一部を切り取ったに過ぎないので、本書の魅力を十分に語れているとはまったく思いません。
この記事を読んで少しでも気になった方はぜひ手に取ってみてください。
きっとあなたのセンスが今よりもグッと開くはずです。
UnsplashのVlado Paunovicが撮影した写真
【著者プロフィール】
著者:田中 新吾
センスは知識からというのはその通りで、その知識を使って「面白いリズム(差異と反復)を生み出すからこそ、いいセンスが発露できるという理解です。
ハグルマニ代表。お客様のビジネスやプロジェクトを推進する良き「歯車」になる。がミッション。命名士(命名総研)、タスクシュート認定トレーナー、栢の木まつり実行委員会事務局長(https://kayanokimatsuri.com) 、RANGER管理人(https://ranger.blog)としても活動中。
●X(旧Twitter)田中新吾
●note 田中新吾

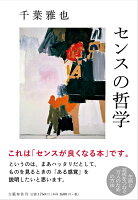









コメントを残す