「あらゆる課題や悩みを楽しみながら、試行錯誤し、工夫やアイデアを重ねて解決にあたる」がモットー。

私が所属している一般社団法人タスクシュート協会には「タスクの先送り」という課題解決を目指す「100日チャレンジ」というカリキュラムがあります。
参考:先送り0で「今日もできなかった」から抜け出す100日チャレンジ
現在第十期が進行中で、タスクシュート認定トレーナーのsugamariさんという方がコミュニティマネージャーを努めておられます。
先日、その第十期のオンラインイベントに招いてもらいまして、5分ほどの短いお話(LT=ライトニングトーク)をさせてもらいました。
その際にお話ししたことの一部をこのブログにも残しておきたいと思います。
*
このような発表の機会があると、あらためて「自分がやってきたこと」や「今やっていること」をまとめようとする動きが生まれます。
日々のタスクに追われがちな中で、「なぜそれをやっているのか?」「どんな思いで取り組んでいるのか?」といったコア的な部分に立ち返る時間が持てるのは、とてもありがたいことだなと感じました。
今回はなんだかとても「誰かの前で喋る」というアウトプット機会の有り難みを強く実感しています。
で、かくいう私は、
「色んなことをやっているよね」
と周囲の人からしばしば言われるですが、私の中では一つのことをやっている意識なのです。
その意識がタイトルにも書いた、
あらゆる課題や悩みを楽しみながら、試行錯誤し、工夫やアイデアを重ねて解決にあたる
です。
これをモットー的なものとして持っています。
外見からは色々なことをやっているように見えるのかもしれません。
でも、突き詰めていくといずれもここに行き着きます。
先日のLTでは、最初にそんな話を自己紹介もかねて少しだけさせていただきました。
*
例えば、
私が「ハグルマニ」というプロジェクト推進支援、プロジェクト伴走支援を行う事業をしているのは、そこに「社内のPJメンバーだけでは期待を超える成果が出せない」や「複雑なプロジェクトなので、思うように進行できるか分からず不安を感じている」といった課題や悩みがあることを実感しているからです。
また、プロジェクトの状況を俯瞰的に見て、必要な歯車になってくれる人が求められていることも具体的にニーズとして掴んでいます。
参考:ハグルマニ
他にも、
私は「命名創研」という活動を現在はハグルマニ事業の一貫として行なっているのですがこれも「いい商品名やブランド名が思いつかない」「新たな名前で仕切り直したい」といった課題や悩みが往々にしてあることに強い実感があるからです。
今年はこの部分をしっかり切り出して明確にしていきたいと思ったりもしています。
具体的にはサービスサイトを作るなどです。
また、
昨年からはじめた「栢の木まつり実行委員会」という活動についても、「地域内において新旧住民の交流がなく、地域の活力が衰退している」といった課題や悩みがあったからこそ、ここを解決していきたいという想いが根底にあります。
いずれにしましても、「課題や悩みに対して楽しみながら、試行錯誤し、工夫やアイデアを重ねていきたい」というモットー的なものが根底にあり、自分の感覚ではそれがアウトプットの段階で形を変わって現れているに過ぎません。
なので、繰り返しになりますが「色んなことをやっているよね」に対しての答えは「そう見えるかもしれませんが、意識としては一つのことをやっている」という答えになる感じです。
そもそも、バラバラなこと同時並行的に進めるのは得意な方ではないため、考えることは少なくシンプルに、できる限り「抽象化」して一つにしていきたいといった考え方が根付いているのもこうなった背景として強いかもしれません。
余談ですが「抽象化」とは、私たち人間の思考を進化させ、営みを発展させてくれる大切な「技術」と理解しています。
「具体と抽象」という本に詳しいです。
これほど役に立ち、人間の思考の基本中の基本であり、人間を人間たらしめ、動物と決定的に異なる存在としている概念なのに、理解されないどころか否定的な文脈でしか用いられていないことは非常に残念なことです。
(中略)
鮪(マグロ)も鮭(サケ)も鰹(カツオ)も鯵(アジ)も、まとめて「魚」と呼ぶことで、「魚を食べよう」とか「魚は健康に良い」という表現が可能になり、「魚類」の研究が進むことになります。
「魚」という言葉(や同等の言葉)を使わずにこれらを表現しようと思うと、いちいち個別の魚の名前をすべて挙げることになります。
さらにいえば、「鮪」という名前も、何万匹といる個別の鮪を「まとめて同じ」と扱っているからつけられたのです。
「いま、○○沖のA地点で群れて泳いでいる先頭の鮪」と「昨日××さんが築地に揚げて、今セリを待っている手前から三列目、左から五番目の鮪」を鮪という言葉を使わずにすべて区別していたら、どれだけ大変なことになるか、文字どおり「想像を絶する」ことになるでしょう。
(中略)
抽象化なくして科学の発展はなく、抽象化なくして人類の発展もなかったといってよいでしょう。
著者によれば、まとめると「抽象化を制するものは思考を制す」ということだそうです。
この言語化は経験則的にも納得感が高いです。
そして、課題や悩みがあったときに、「自分だったらこういう提案ができる(=自分なりの答え)」といったものが明確にある場合のみ事業や活動にしています。
このようなものが見出せない場合は潔く手放す。
こういうスタンスです。
私がモットーとしているのは「あらゆる課題や悩みを楽しみながら、試行錯誤し、工夫やアイデアを重ねて解決にあたる」というものです。… pic.twitter.com/MbS7rBhRyy
— 田中 新吾 (@tanashin115) April 1, 2025
引き続き、「あらゆる課題や悩みを楽しみながら、試行錯誤し、工夫やアイデアを重ねて解決にあたる」がモットーに、日々発生することに取り組んでいければと思います。
今回のお話が何かの参考になれば幸いです。
UnsplashのJESHOOTS.COMが撮影した写真
【著者プロフィール】
著者:田中 新吾
チェスはほぼやったことがなのですが、タイトル的にイメージに近そうなのでアイキャッチにさせてもらいました笑
ハグルマニ代表。お客様(法人・個人)のプロジェクトの推進支援と伴走支援がメインの仕事⚙️ / 命名創研、タスクシュート認定トレーナー、栢の木まつり実行委員会、ProjectSAU、RANGER管理人としても活動中🌱 / 「あらゆる課題や悩みを楽しみながら、試行錯誤し、工夫やアイデアを重ねて解決にあたる」がモットー。
●X(旧Twitter)田中新吾
●note 田中新吾

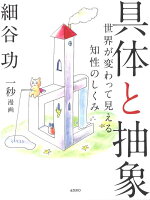









コメントを残す