成熟した大人になるために、子供であることが必要になる!?原動力は好奇心。

ある女性が、
「私、人の気になるところによくイラッとすることが多くて〜。で、そんな自分が嫌になることがあるんです〜」
と切り出した。
私は、それは誰もが多かれ少なかれ持っている感性であって、この感性が備わっているから、人は危険を避けて生きてこれたんだ、といったいつもどおりのものが思い浮かんだ。
人は、危険を避けるために、嫌なところ=危険なところを瞬間的に見抜くようにできている。
同時に、今の時代にしてはその危険度合いに対して過剰反応だと感じられることも多いのだが、それは過去の名残りなのだろう・・・そうも感じる。
以前これと同じようなことをこのブログに書いたことがあった。
この女性の話を私と一緒に聞いていた若い男性(こちらはイラッとすることはあまりなさそうに見えた)に聞いてみると、
「(私は)人の良いところを見るようにしているんです。」
と返ってきた。
なるほど、それならば先ほどの女性のようにイライラすることは少ないんだろう。
でも良いところばかり見るということは、騙されやすい、というのがまたセットでくっついているんだろう、そんな風に同時に感じた。
そしてたまたまこの二人に、警戒と無警戒という両極があるように感じられて、それは私の中にも両方があって、日々、こっちに寄ったり、あっちに寄ったり、状況に適応しようとしているのを感じたのだ。
適応と言えば賢げな言葉だが、実のところいつも迷っている、と言った方が正しい表現なのかもしれない。
警戒過剰だと疲れるし、無警戒だとやられてしまうし、やはり生きるというのは何とも複雑なものだとあらためて思う。
ユングの精神的成熟
ネット動画に「カール・ユングの教え」なるものがある。
今回目についたのは、「実年齢よりも若く見える人」についてのもの。
ユングは、若く見える人の精神的な深みははるかに成熟していることがある、という。
これが本当ならば、肉体的老化が、精神的成熟とは関係ない、ということになるわけだ。
さて、どうだろうか?これは共感できる内容だろうか?
むしろ、そのシワに数々の経験が刻まれているように感じるし、その経験にリスペクトを持って、年上の人は敬うものである、と日本人は教わってきた。
だから私の場合、なんとなくだが年を重ねること=精神的成熟と捉えていたように思うのだが・・・
でもよくよく思い出してみると、先輩にもいろいろな人がいたし、既にかなり年を重ねてきた自分自身が精神的に成熟しているかと言われれば、とてもそうとは思えない。汗。
そもそも精神的成熟とは何なのだろうか?
それを測る尺度も難しいのだが・・・。
ーーーーーーーー
ユングは精神的成熟を「人生の複雑さを理解すること」というように捉えていることがわかる。
そして、この人生の複雑さを理解することが、人生を意味あるものにする、と言う。
年齢を重ねることで、人生の複雑さを理解する、ということももちろんあるとは思うが、「実年齢よりも若く見える人」は子供のような旺盛な好奇心でもって、自分や社会、そして人生というものを探求しようとする才能を持ち合わせているらしい。
その探求が、インスピレーションを与え、結果的に人生の複雑さを理解することになるということだ。
私がこれまで精神的成熟という言葉に感じていた印象は、達観した落ち着いたイメージであったが、これを聞くとむしろ子供のように落ち着きない、といったような部分がある、という全く異なる印象になる。
なるほど、精神的成熟は「人生の複雑さを理解すること」だと定義すると全く見え方が変わる。
これを一旦信じて考えてみる。
確かにここまで世の中を見渡してくると、精神的成熟なるものを最初から持って生まれてくる人は、わずかなのだろう、ということは理解できる。
そして、それ以外の大多数の人は、精神的に成熟するまでの行程は落ち着きのない試行錯誤の時間である、ということに対しても違和感はない。
たぶん、ああでもない、こうでもないなどと理解しようとするうちに、経験済みのものだけに対して、外からは落ち着いているように見えるということなのだ。
少なくとも、自分においては落ち着いていては何も得られないというなぜだか確信のようなものを持っていて、
落ち着いたフリをすることは落ち着くことを逆に、遠ざけるのだ!
むしろ、そう自分に言い聞かせたい。
インナーチャイルドを育む
ユングの動画には、インナーチャイルドというワードも出てくる。
インナーチャイルド→心理学における「内なる子ども」の概念で、幼少期の経験や感情が心の奥に残り、大人になっても感情や行動に影響を与える部分。
子供の頃に愛されなかったり、十分に満たされない思いが残っているから、大人になってからも衝動的に反抗的行動を起こしたりしてしまうことがある。
なので、そうならないためにインナーチャイルドを癒す必要がある、などと言われる。
ユングによると、精神的成熟のためには好奇心が必要ということで、本来ある好奇心を抑制しないために、インナーチャイルドを育む必要がある、のだと言う。
インナーチャイルドについては、“癒す”という言葉ばかりをよく聞くものだから、”育む”という言葉が妙に気になった。
子供を否定することでもって大人たらんとしてきたはずだったのではないか?
大人になってまで、インナーチャイルドを育むとは具体的にどうするものなのだろうか?
ワガママ、イタズラ心、フザケたい気持ち、どうでもイイようなことなのになぜだか妙に気になってしまう気持ち、などなど大人がやらないこと、やったらいけないことになっている感覚を大切にする、ということなのかもしれない。
そう考えていくと自分がシックリくる感覚は、「なんで?」。
(自分が)疑問に思うこと、納得できないこと。
これを明確に意識して、それに対して納得するものを見つけようとすること。
自分にとってこれが、インナーチャイルドを育むこと=好奇心を抑制しない、ということなのだと思った。
考えて行き着いたところは、全く当たり前のところだった。汗。
ただ、この「なんで?」が素直に出てくるには、日頃から、ワガママ、イタズラ、フザケたい気持ちなどを解放する土壌を造っておく必要があるようにも感じる。
これまで、自分の中にあるインナーチャイルドを意識したことはなかったのだが、インナーチャイルドという言葉を意識して自分を眺めてみると、自分の中のインナーチャイルドが浮き上がってくるように感じ、どこか自分に大人という感覚が湧かない理由が説明できるように思った。
原動力は好奇心!
ここまでのユングの話を今一度なぞると、精神的成熟のために、好奇心が必要で、そのためにインナーチャイルドを育むことが必要、ということになる。
これは、精神的に成熟することを大人になる、と表現した時に、大人になるために内なる子供が必要だ!と言っていることに他ならない。
また、何ともパラドックス的。
これもまた、誰もが勘違いしそうなトラップのようなところだ。笑。
とかく大人という者は、答えを知ってないといけない、というプレッシャーに晒されるものだ。
年をとれば尚更だし、役割を持っても尚更である。
それで答えをある納期までに見つけなければならないと追い詰められて、同時に答えがわからないことに恥ずかしくもなって、答えがわかったということにしてしまって、あるいは答えがわかった気になって、探求を終わらせてしまう。
納得していない自分がどこかにいるにもかかわらず
・・・。
それを繰り返すうちに、好奇心がなくなっていくのではないだろうか?
答えを出していくことでひとつひとつ完了させて行くことが人生である、と捉えるのではなくて、答えを出すもののそれはあくまでも一旦の仮りであって、納得いかないところがあるのならば、なぜだろう?こうなのかも、いや違うか?などと探求し続けることが人生である、と捉えることもできる。
そんな風に捉えて好奇心でもって、複雑な人生を理解すると、より人生を味わうことになって面白さが増幅されるように感じる。
ーーーーーーーー
さて、今回のことは、「精神的成熟」という言葉の定義をユングによってちょっと変えられただけで、見方がガラッと変わった、という風に見ることができるのだろう。
これがまさにユングのいう「探求が、インスピレーションを与え、結果的に人生の複雑さを理解することになる」ということの一例と言えるのではないだろうか?
そして、今回のユングのメッセージは、いくつになっても大人になりきれていないように感じる自分を肯定してくれるものでもあった。
またまた自分が納得する、自分に都合の良い結論となってしまった。汗笑。
最後に
冒頭の警戒と不警戒の両極のもの。
これもお二人からいただいたひとつのインスピレーションだろう。
人は何に警戒するのか?
何に不警戒なのか?
なぜ人はそれに警戒するのか?
なぜ不警戒なのか?
それらを納得するまで好奇心を持って見つめる。
女性がイラッとするようになったのは、何かキッカケがあったんだろうか?
若い男性が、人の良いところを見るようになったのは何故なんだろうか?
などなど・・・・・
そして、探求の結果を反映させて、また自分なりの警戒と不警戒の間を渡り歩く。
やってみて、また修正を加える。
正解というものは、結果論でしか語られないものではある。
しかし、不警戒でいなければチャレンジはないし、警戒がなければ危険が一杯である。
一旦納得したとしても、また失敗もするだろうし、探求し続けたとしてもたぶん結論が出ないかもしれないが、それでも、ああだ、こうだと納得するところを探し続ける。
人生それでいいのだ!
ユングに、そう強く後押しされたように感じた。
【著者プロフィール】
RYO SASAKI
工学部を卒業後、広告関連企業(2社)に29年在籍。 法人顧客を対象にした事業にて、新規事業の立ち上げから事業の撤退を多数経験する。
現在は自営業の他、NPO法人の運営サポートなどを行っている。






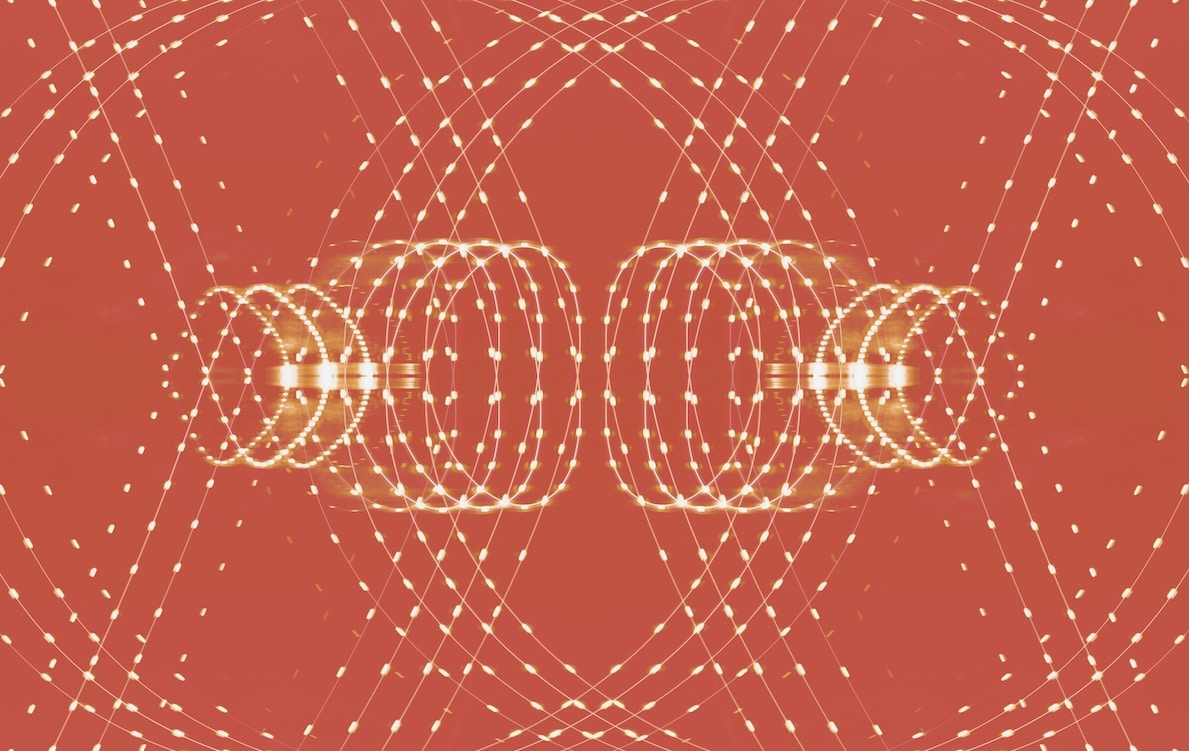



コメントを残す