「関係性の構築、発見、理解は、新しい価値創造や深い洞察に繋がる」という信念について今思うこと。

私には、以前から「関係性の構築、発見、理解は、新しい価値創造や深いに繋がる」という信念があったのですが、最近になって「関係性」という概念にさらに強い関心が向いています。
思うに、AIが様々な仕事を代替してくれるようになってきたことが影響していそうです。
ということで、今私なりに関係性について思うことを残しておきたいと思いました。
まずは、これまで持っていた信念についての解説から。
最初に、関係性の構築について。
関係性の構築とは「AとBの間に、新しい橋をかける」みたいなことです。
これは人間関係で考えると分かりやすいと思います。
要するに、これまで繋がっていなかったAさんとBさんを繋げると、その間に新しい橋がかかるということ。
ObsidianやCosenceでノートとノートをリンクで繋ぐこともこれに類することだと思います。
関係がなかったモノ同士を繋げる、繋げてみる、ってことですね。
これが関係性の構築。
次に、関係性の発見です。
これは「AとBは、実はこういう一つの線で結ばれていた」みたいなことなのですが、これも人間関係で考えると分かりやすいと思います。
先ほど繋がることができたAさんとBさん。
お互いの共通点を探していくと、なんと「沖縄県出身」という共通点があることが分かったとします。
これが関係性の発見です。
関係性を構築するからこそ、関係性が見えてくるという流れになっていると思います。
少し話は変わりますが、数年前に「大人のおしゃぶり」というめちゃくちゃバズった投稿がありました。
これはスマホを手番せない大人の様子と、
おしゃぶりを手放せない赤ちゃんの様子が共通である、という関係性の発見から生まれた言葉です。
「たしかにそうだ!」という大きな共感を呼び、話題になりました。
私もめちゃくちゃ秀逸だなと思いました。
そして、最後に「関係性の理解」について。
関係性の理解とは、単にAとBが繋がっている、という表面的な事実を知るだけに留まりません。
その関係がどのような背景や文脈の中で生まれ、どのような歴史や経緯を経て現在の形になっているのかを深く掘り下げていくイメージです。
また、関係性には「長さ」や「太さ」といった質的な側面も存在します。
長い時間をかけて築かれた信頼関係や、深い共感によって結ばれた強い繋がりもあれば、表面的で一時的な関係もあります。
こうした関係性の質や強度、さらにはその変化の過程までを理解したり追求することで、単なる「繋がり」を超えた本質的な洞察が得られるのかなと。
私が好きなのはtwitterの時代に投稿した以下のポストです。
アッシュと英二の名前がつかないけど太い関係性がかっこよすぎて。 https://t.co/ylWdHuoVDQ
— 田中 新吾@ハグルマニ (@tanashin115) December 21, 2018
これが関係性の理解です。
私の関係性に関する信念の下支えになっているのは、ノースウエスタン大学の心理学教授のデドレー・ゲントナー氏の考えです。
「さまざまなことを関係で考える能力こそが、人間が地球を支配している理由の一つだと思う。」
「他の種にとって、関係を理解するのはかなり難しい。」
さて、いかがでしょうか?
他の種にとって関係を理解するのは難しい、というのであれば関係に注力してこそ人間らしいと言えるのではないかと思うのです。
一方、現代にはAIという優れたツールがあり、そんなAIも関係で考えることができたりします。
この先の続きを書いて、というプロンプトに対して出力をするということはまさに関係の構築だと思います。
しかし、なんでもかんでもAIに任せて関係性を構築したり、発見したりすればいいわけではなく、人間がやるべき関係性の構築、発見、理解があり、AIに任せた方がいい関係性の構築、発見、理解があるということではないかと思ったりしてます。
人間がやるべきところをAIにやらせると、納得感が得られず、深い洞察には繋がらない。
一方、AIに任せればいいところを人間がやろうとすると途方もない時間とお金がかかるみたいな。
とはいえ、完全に分断されているわけではなく、きっとグラデーションなのだと思いますが、この辺をもっと深ぼっていけたらいいなと思ったりしています。
UnsplashのMario Häfligerが撮影した写真
著者:田中 新吾
◼︎ハグルマニ / 命名創研 代表 大企業様、中小企業様、ベンチャー企業様、NPO法人様のプロジェクト推進に必要とされる「歯車に」なったり、「#名前座」の構築によるブランディング支援をしたりしています。
◼︎#栢の木まつり 実行委員会 委員長(地域づくり事業@入間市宮寺)
◼︎タスクシュート認定トレーナー









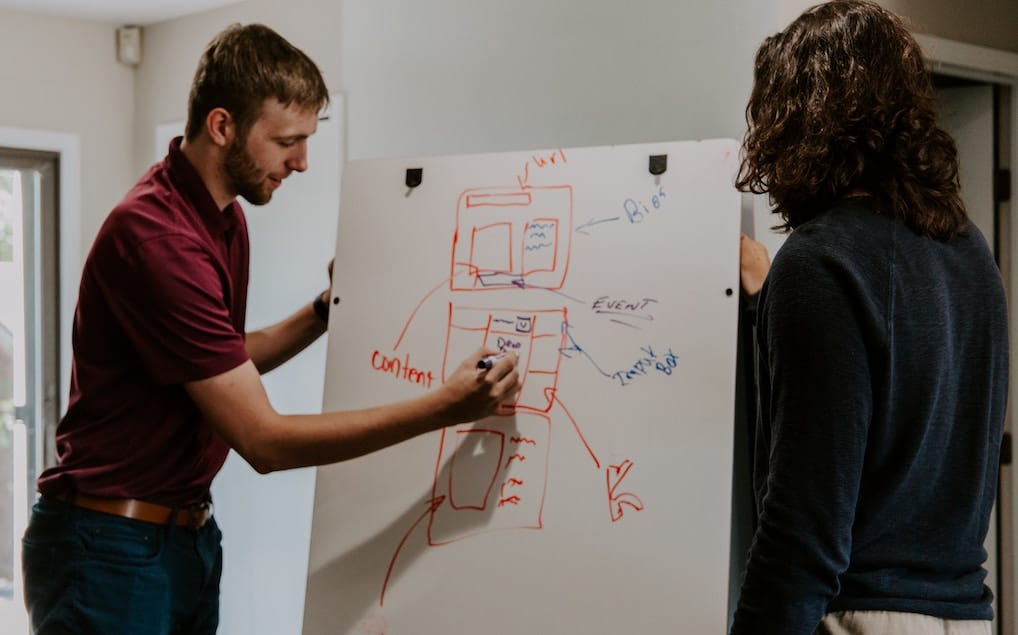
コメントを残す