39歳で、学習の仕方を根本的に変えることになった話。
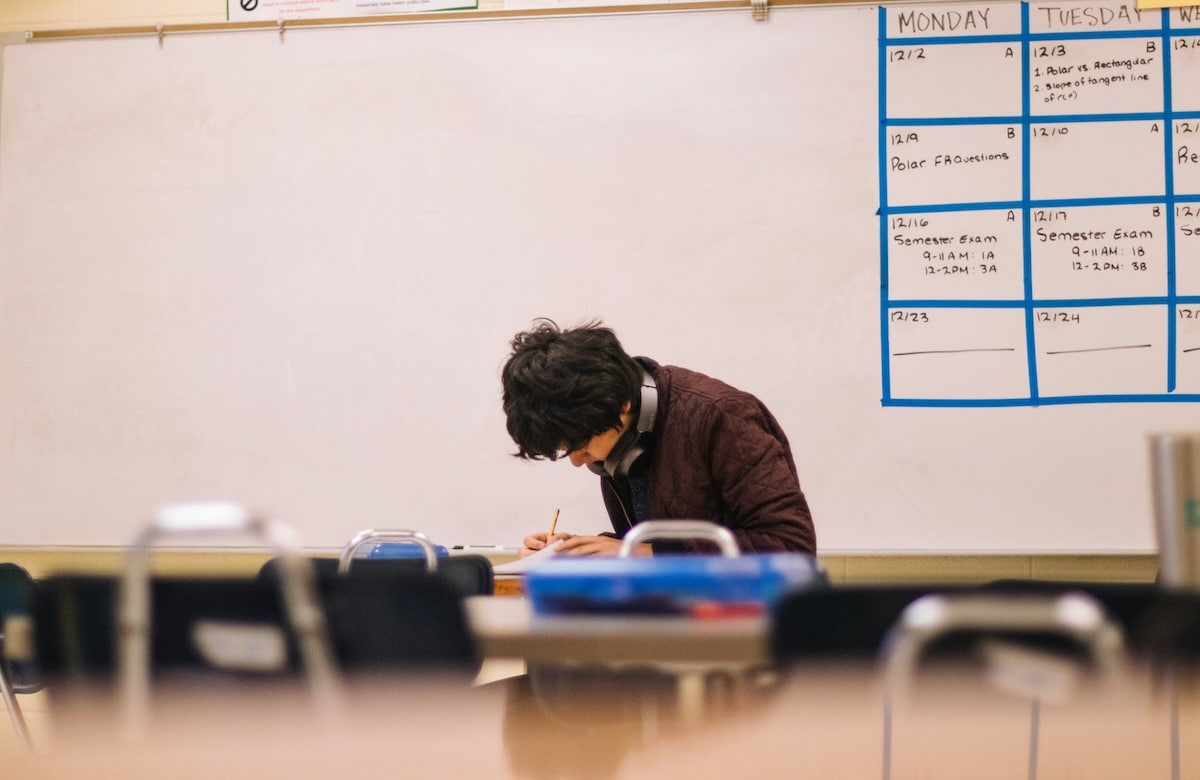
39歳になり、学習の仕方を根本的に変えることとなった。
きっかけは「10X情報処理エキスパート講座」というオンライン講座への参加である。(現在も参加中で、11月上旬まで続く)
この講座では、従来の「ノウハウコレクター」的な学習から脱却し、「探偵のマインド」で情報選抜してを扱うことなどを学んでいる。
そして、10X情報処理の中核にあるのが「アクティブリコール」と「分散学習」という学習法だ。
*
アクティブリコールとは、簡単に言えば「何も見ずに自分の頭から内容を書き出す」こと。
10X情報処理エキスパート講座のグループセッションの主な流れは以下である。
- 学んだことについて何も見ずに自分の頭から内容を書き出す
- その後、講座やメモや課題図書を見ながらフィードバックを受け、内容をブラッシュアップする
- それをObsidianのメモに残し、自分の言葉でまとめる
さらに重要なのは、このプロセスを分散学習として実践することだ。
つまり、一度にまとめて学習するのではなく、時間を空けて何度も復習する。
エビングハウスの忘却曲線に抗い、記憶の定着を最大化する学習法である。
この二つの学習法は、私にとって非常に刺激的で大きな発見であった。
なぜなら、これまでの私は「読んだつもり」「聞いたつもり」で終わることが多かったからだ。
アクティブリコールを実践することで、自分が本当に理解できている部分と、そうでない部分が明確に分かるようになった。
そして、理解できていない部分を重点的に復習することで、学習効率が格段に上昇。
さらに、分散学習により、一度に詰め込むのではなく、適切な間隔で復習することで、長期的に記憶へ定着させる仕組みも整った。
何よりも、これらが科学的根拠に基づいている最強の学習法というのが大きな驚きだった。
*
この学習法を自ら実践する中で、短歌を詠んだ(実は俵万智さんの影響で時々単価を読むようになった)。
学び方 三十九で 改める
アクティブリコール 第二の人生 歩み出す
39歳で学び方を変えることへの感慨と、新しい学習法への期待を込めた歌だ。
いかがだろうか?
実際、アクティブリコールと分散学習を続ける中で、確実に「第二の人生」が始まっている実感がある。
*
アクティブリコールと分散学習の組み合わせは、学習効率の向上だけではない効果をもたらす。
この学習法を続けていると、自分の思考パターンや理解の癖が見えてくるのだ。
そして、時間を空けて復習するたびに、新たな発見や気づきが生まれる。
たとえば「フラクタル」という概念を知ったとき、最初は「部分と全体が似ている」という程度でしか理解できていなかった。
部分と全体、フラクタルな構造。
— 田中 新吾(ハグルマニ / 命名創研 / 栢の木まつり) (@tanashin115) January 19, 2017
しかし、アクティブリコールと分散学習を組み合わせて何度も学習を重ねていくうちに、フラクタルが「80:20の法則」や「べき乗則」とどう関連しているのか、さらに「スケールフリーネットワーク」との関係性までくっきり見えてきた。
これは思うに、単に情報をインプットするだけでは絶対に得られない理解の深さだ。
*
また、アクティブリコールと分散学習を実践する中で、「わかる」という状態の本質についても気づきがあった。
橋本治さんの『「わからない」という方法』の中に、次のような記述がある。
「わかる」とは納得することである
「わかる」とは、順を追って理解して行くことである。
そうすることによって、学ぶ側に「納得」が起こる。
「わかる」とは納得することなのだから、「分かっていくプロセス」とは、「我が身を納得させる時間」に等しい。
アクティブリコールと分散学習は、まさにこの「我が身を納得させる時間」を生み出す学習法の最たる例と言えるだろう。
頭だけでなく、心と身体も含めた「我が身」全体で納得できるまで、時間を空けながら何度も書き出し、整理し、そして再構築する。
このプロセスを経ることで、本当の意味での「わかる」がやってくる。
ブツブツ口に出しながら思い出すアクティブリコールのことを「プロダクション効果」というのだが、口に出すとまさに我が身を納得させている感じがする。
*
また、アクティブリコールと分散学習を続けていると、学習に対する姿勢も変化する。
以前の私は「たくさんの情報を集めること」に価値を置いていたが、今は「少ない情報を深く理解すること」の方がはるかに価値があると感じている。
これは「Less is More」という考え方とも一致する。
情報の8割を捨て、残りの2割に力を注ぎ深く理解する。
アクティブリコールと分散学習の組み合わせは、この「2割を深く理解する」ための最強の組み合わせだと思う。
*
39歳で学び方を変えることは、正直なところ最初は不安であった。
「もう遅いのではないか?」「今さら変えても意味がないのではないか?」という気持ちもあった。
しかし、いざやってみるとアクティブリコールと分散学習を実践する中で、年齢は関係ないことが分かった。
何をやるにしても遅すぎることはないのだ。
随分前に書いた以下のブログを思い出す。
むしろ、これまでの経験があるからこそ、新しい学習法の効果をより深く実感できるのだと感じている。
*
現在鋭意、アクティブリコールと分散学習を日々の学習に組み込んでいる。
読書の際も、講座受講の際も、必ずアクティブリコールのプロセスを経り、適切な間隔で復習する。
その結果、以前よりもはるかに深い理解と新しい発見が生まれるようになった。
39歳で学び方を変えることは、決して遅いことではなかった。
むしろ、これまでの経験を活かしながら、より効果的な学習ができるようになった。
アクティブリコールと分散学習は、私に「第二の人生」を歩み出す勇気と方法を与えてくれた。
この学習法、もっと早くに知りたかったなと切に思う。
これからも、この学習法を大切にしながら、新しい発見と成長を続けていきたい。
UnsplashのJeswin Thomasが撮影した写真
【著者プロフィール】
著者:田中 新吾
その他に、自己説明、精緻化質問、生成効果、描画効果など効果のある学習方法を知ることもでき、最近大きな充実感を得ています。
◼︎ハグルマニ / 命名創研 代表 大企業様
中小企業様、ベンチャー企業様、NPO法人様のプロジェクト推進に必要とされる「歯車に」なったり、「#名前座」の構築によるブランディング支援をしたりしています。
◼︎#栢の木まつり 実行委員会 委員長(地域づくり事業@入間市宮寺)
◼︎タスクシュート認定トレーナー
◼︎Obsidian×10X情報処理












コメントを残す