「まず先に感謝から。」は、すべてを受け入れるところからスタートして可能になる。

神社仏閣に参拝して、神様仏様に願い事をする。
日本では当たり前の風習だ。
ところがいつ頃からだろうか?
「お願い事をしてはいけない」と言う説をよく聞くようになった。
神社仏閣は、お願い事をせずに感謝を伝えるところだという。
加えて、住所も伝えないと神様仏様に誰の願いなのか届かない、というのもある。
私の場合、これまで長きに渡って、住所はもちろんのこと、名前すらも名乗ることなく願い事をし続けてきた。
だから、そんなことを今更人生の終わりの方に言われても、どうしたらいいんだろうか?汗笑。
新説を初めて聞いた時、正直そう思った。
そして、初めにまず感謝しよう、などとはとても思えない、とも思った。
ご利益を受け取ったことに有難う、というのが普通で、受け取っていないのに有難うというのは、非常識だろう?
教育よろしく、私にはそんな強い価値観が備わっているのだ。
だが最近になって、この新説というものの意味するところが自分なりにわかるような、そして、備わっている強い価値観を手放せそうな気がしている。
そして、この変化はわずかなものかもしれないが、実はものすごく大きなものではないか?
そんな予感もある。
それは、今までとは別の歯車が回り始めたみたいな感覚だ。
相変わらず大げさだし、しかもまだ兆しのようなものなのだが、拙速にも今感じているところを書いてみたい。
新説が本来の作法!?
新説と言ったが、ある本によるとこれこそが本来の作法らしい。
そもそも「祈り」の本来の意味は、「意」に「宣」と書き、「意宣り」であり、「意のままに沿う」こと。※「意を宣言する」という説も他にある。
「祈り」は「あなたの仰せに従います。あなたが望むように生きています。ありがとうございます」という意味。
そして「願い」は、「ねぎらい」が語源。「ねぎらい」とは、「希望を叶えてください」ではなく、「よくしてくださってありがとうございます」と感謝するという意味だったらしい。
かの空海もまた、みんな順番が間違っていて、ご利益は今生きていることに、まず感謝することによってついてくる、というようなことを言っていて、これと符号する。
歴史はよく改ざんされるものであるようだが、なぜだか言葉の意味も時代とともに変わっていくようだ。
もしこの説がホントなら、この「願う」という言葉の変わり具合は真逆に近くて、私はまたもやとんでもない固定観念をつかまされていたんだ・・・・と、もはや笑うしかない。
ただ、この新説(本来の説?)にもまた気になるところがあって・・・。
あなたの仰せのとおりのあなたとは、誰なのか?(※私は無神論者である)
仰せのとおりとは、ずいぶん受け身な生き方、そもそもそれでいいんだろうか?
神様は住所という記号システムを各国語毎に理解しているんだろうか?
住所を伝えるのは、見返りを期待しているからであって、ならば暗に願っていることと変わらないんではないか?
更には、神社仏閣で御守りやお札を販売しているのは何らかのご利益を願う商品なわけで・・・この商品が放置されていることにも、私にはシックリ来ない・・・。
まあ、神様がいるならば、こんな風にいろいろとイチャモンをつける者には当然ご利益を与えないんだろう。笑。
それでも、私というものはどうしても疑ってしまうのだ。
微妙な話ばかりだが、先に感謝せざるを得ない
ここから、ここ最近私に立て続けに起こった微妙な出来事を紹介する。
これらの出来事が、この新説の意味合いが少しわかった気になったキッカケだった。
①同じ男性によく会う
少し前に飲み屋で知り合った男性がいる。
この男性は東北出身で田舎が私と近い。
ある日曜の昼下がり、自転車で通ったことのない初めての道をどんな店があるんだろう?と観察しながらゆっくり進んでいると、前からこの男性がやってきた。
飛ばしていたら気づかなかったが、ゆっくりだったので気づいて声をかけると、その男性もほとんど通らない道だという。
そしてまた別の日曜日、最近オープンしたという飲食店に意を決して、初チャレンジした時のこと。
その店の前に到着した時、ある男性が入口のドアを磨いている。
目が会うとそれがまた、この前の男性だった。
聞くところによると最近この店の手伝いをし始めたらしい。
何かサービスしてもらえたわけではない。
初めての店に入る緊張が少し和らいだくらいのものだ。笑。
②合った男性は私が加入した保険の設計者
とあるお店で食事を始めると、前回もこの店でお会いしたその店の常連の男性が入ってきた。
その男性の仕事が保険関連と知って、私は自分が最近新しく加入した保険のことを話した。
加えて、懸念しているインフレと米ドルのことを話したんだと思う。
すると、その男性は私が加入した保険の会社に以前勤めていたことがあって、しかもその時に私が加入した保険商品を設計していたことが発覚する・・・。
「その商品、私が作ったんですが、あまり会社の利益が大きくない商品なんで、購入者からするといいんではないですかね?」だと・・・。
私がこの保険に加入したのはその1週間前のこと。
そんなことがあるのだろうか?
でも、これといって大きな得があったわけではない。
ややお得な商品だと聞いて、少し安心したくらいのものだ。
そんな設計者と会っても会わなくても、インフレも米ドルも変わりはしない。笑。
③美味しくない、と言ったワインを隣の人からご馳走になる
あるワインバーでの宴が活況になった時、私の連れとその店の店主が、ワインの話をし始めた。
テーマは、多品種のブドウを混ぜて造るいわゆるブレンドワインについてで、いいところが補間し合うし、角が取れて美味しい、というようなことで盛り上がっていたと思う。
私はそれに対して、真っ先に浮かんだことでもってその話に割って入る。
「私は、白ブドウで作ったワインと黒ブドウで作ったワインをブレンドしたものは嫌いです!」
私は、2回目ほど白黒のブレンドのものを飲んだことがあって、正直美味しいと思わなかったのだ。
すると、それが隣の席のご夫婦にまで聞こえてしまったらしく、微妙な顔をしたご夫婦が私にワインを勧めてきた。
ご夫婦が飲んでいたワインが、まさに白ブドウと黒ブドウをブレンドしたワインだったのだ。
私は気まずく思いながら、恐る恐るいただく。
すると・・・これは美味い!
私の先入観はあっという間に壊れたのだった。汗。
そのご夫婦は苦笑いしながら、ならばもう一杯と更に勧めてくれた。
それをキッカケにしてご夫婦と話が盛り上がり、逆に世の中は忖度した言葉で溢れている、と私をフォローしてくれたりした。
後から店主から聞いたのだが、いただいたワインはかなり高額なものだったらしい。
美味しいわけだ。
口は災い元が、歯に衣着せぬ、で好転した瞬間だった。
ちなみに、今は白黒のブレンドワインはそんなに多くない。
そんな低い確率をまた引き当ててしまった。
・・・・・・
どれも確率の低い話だが、微妙な話だ。
これ以外にも私の周りでは確率の低い話がいろいろと起こって、単なる偶然だと片付けたいのだが、それにしても多い、というのが正直なところだ。
宝くじでも当たったのであれば、ハッキリするのだが、得と言えばワインをいただいたことくらいで、だからどうした?という微妙なものばかりではある・・・。
ただ、これだけ確率の低い面白い巡り合わせがたくさん起こるというのは、それがいくら微妙なものであっても、私にとって世の中は楽しくて、温かいものだ、と感じさせてくれる。
なんだか面白く温かい偶然の出来事に常に包まれて生活させてもらっているように感じられてくる。
そしてそう感じると、最初に何かが得られない限り「ありがとう」とは言わなかった私でも、今に感謝できるような感覚になってくるのだ。
受け入れることで、先に感謝できる
このような出来事が最近立て続けに起こっているのは、自分に何らかの変化があったからだろうか?
思いを巡らせてみると・・・
強いて上げるならば、自身に素直でいて素直な自分に抗わず、自分の不甲斐なさを受け入れて、周りの人もそこからのご縁も受け入れる(常に相手の個性を探す、お誘いは断らず、おすすめは試す)という具合に、縁にも抗わないでいる。
多分に感覚的なものがあるから、言葉では伝わり切らないようにも感じるのだが、言葉にするとすればそんなようなところだろうか・・・。
以前から試みていたこともあるが、それが定着してきているのかもしれない。
※ちなみに、自分に素直でいる、と言っても簡単ではない。これについては前回の個性化のブログを参照のこと。
自分が目的を持たず、何も求めず、人にも何かを求めず、苦手なことや嫌いなことに出会っても、何かの発見があるはず、という好奇心をもってすべてを受け入れる。
聞かれれば自分のことをできるだけ正直に話す。
恥ずかしいことも不快にならない程度にぶっちゃける。
できるだけ作為せずに感じたまま反応する。
こんな具合で自分がご機嫌でいられることによって、どうやらいろいろなことが自然に起こっているのかもしれない。
例えば、何かの目的を一心不乱に追いかけている時、そこにはその目的に届かないという欠乏があって、その欠乏に不安やイライラを感じているようなことがある。
そんな状態ではそのような出来事には出会えないようにも思う。
・・・・・・
さてここまで来ると、ここまでのことが新説(本来の説)の「祈り」の「意のままに沿う」という言葉のニュアンスに重なってくるようにも感じられる。
これは、欠乏を感じると欠乏のままであって、欠乏という感覚がなくなると欲しかったものがいつの間にか手に入っていた、といったような感覚にも通ずる。
“受け入れる”ことができればご機嫌で、ご機嫌でいれば人は周りの面白さと温かさに包まれる。
面白さと温かさに包まれれば感謝できて、感謝できれば更にご機嫌になる。
こんなサイクルが宝くじに当たらずとも、ご利益を得るサイクルのように感じられてくる。
そしてこのサイクルのスタートは何と言っても”受け入れる”ことだ。
“受け入れる”といっても、世の中には受け入れられないものが山のようにある。
納得がいかないこと、苦手なこと、嫌いなこと、酷いこと・・・。
“受け入れる”とは、納得する、苦手を克服する、好きになる、ということではない。
納得いかない、苦手、嫌いのままでそれらをまず理解することだ。
そんなこと、そういう人、そういう立場の人がいるかもしれない、こんな背景があったのかもしれない、という想像と理解である。
自分ならそんなことはやらない、と思ったままでいい。
そして、受け入れられないものを別の面からみること、受け入れられないものとの距離を置くこと、受け入れられないものを忘れること、こうしたいくつかの手法を行使した上でも私は、十分に受け入れている、とすることにしている。
受け入れられないものを自身によって失くすことができない状態であるのならば、失くそうとする目的が生まれ、そこに欠乏が生じてしまう。
それではご機嫌でいることはできないから、受け入れている、とは欠乏がない状態と言った方がいいのかもしれない。
・・・・・・
さて・・・とりあえず拙速にまとめてみたのだが、これが近況で私が感じた、今に感謝できるようになってきてるんではないか?と思われる経緯である。
私の場合、ここまでしないと神社仏閣の新説を信じることはできない。汗笑。
そして、今に感謝できない私はここまで欠乏を貪る病を患っていたのかもしれない、そんな思いがもたげてくる。
まあ昔はともかく、これからはこの調子でご機嫌のまま、世の中の面白さや温かさに包まれて生きたいものだ。
【著者プロフィール】
RYO SASAKI
欠乏貪症(造語)は、今の瞬間を生きていないとも感じます。
工学部を卒業後、広告関連企業(2社)に29年在籍。 法人顧客を対象にした事業にて、新規事業の立ち上げから事業の撤退を多数経験する。
現在は自営業の他、NPO法人の運営サポートなどを行っている。








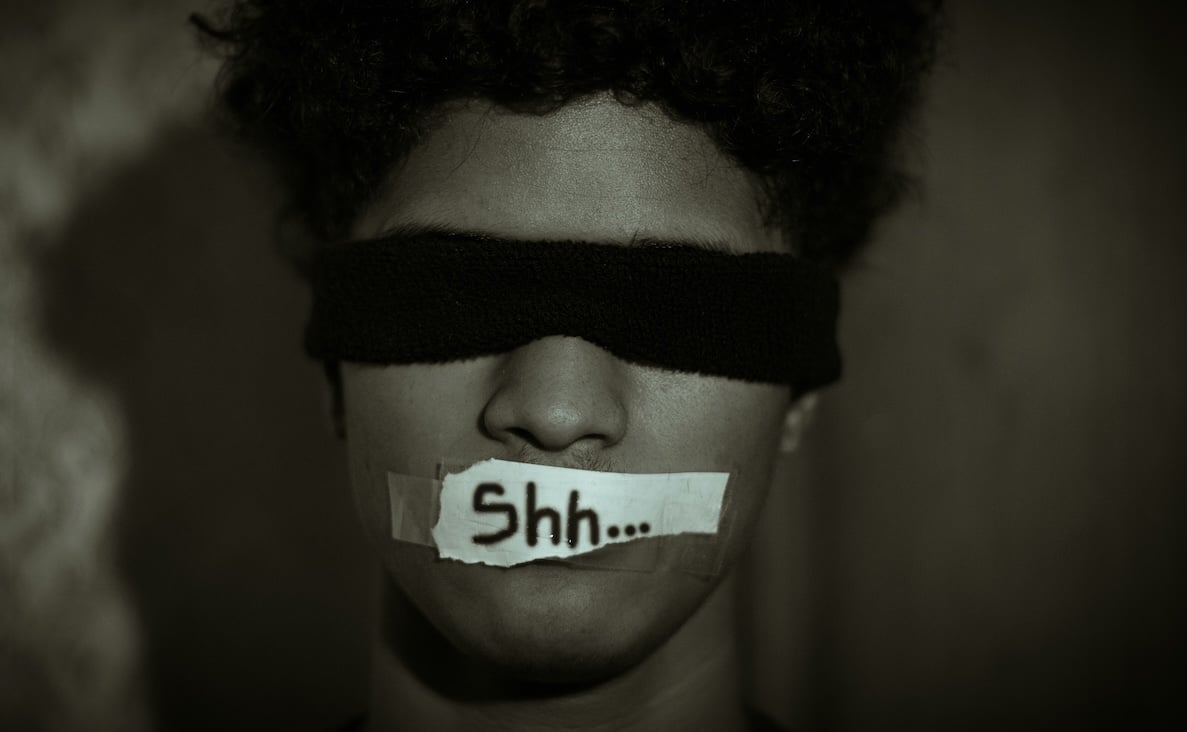

コメントを残す