「やる気」と同じくらい「やった気」も、習慣化においては注意点として話題に上がっていいのではないか。

2024年3月からタスクシュート協会が運営する「ユタカジン」というnoteマガジンに月に1回のペースで寄稿をさせてもらっています。
最近投稿した記事でちょうど丸1年を迎えました。
今回投稿したのは「「誰かの時間の使い方」を、積極的に真似していく」というもので、「真似する思考」的な内容といってもいいかもしれません。
「誰かの時間の使い方」を、積極的に真似していく【ユタカジン】
複数の方からこの記事についての感想やコメントを頂戴している中で、一つとっても有難いものをいただきました。
それがこちらです。
タナシンさんの記事からは、真似する相手から感じ取った「よさ」を、自身で丁寧に取り入れるところも含めて共感や敬意を感じて素敵だなと思いました。
— うさぼう@TC認定トレーナー (@usabo_tweet) March 1, 2025
あと結構長めの時間軸で取り入れていくあたりもタナシンさん「らしさ」のように感じます。
4/19のジャンクションも楽しみです! https://t.co/T1x3X5Rspd
特に刺さったポイントは「結構長めの時間軸で取り入れていくあたり」という部分でした。
今回はこのいただいたコメントを契機に考えたことを少し残しておきたいと思います。
*
伊坂幸太郎のゴールデンスランバーの中に「人間の最大の武器は、信頼と習慣だ」という話が出てきます。
この考え方について反対意見を持つ人は少ないのではないでしょうか?
2つの武器のうち「信頼」の方は「人間関係」によって作られるものであるためアンコントローラブルです。
しかし、「習慣」の方は個人でかなりコントロールができます。
実際のところ私もブログを書いたり、白湯を飲んだり、筋トレをしたりとこれまでに様々な習慣を作ることに成功してきました。
一方、成功の反面、習慣化に失敗してきたものちゃんとあり、そこにはある共通項があります。
それは「公言してしまった」というものです。
一体どういうことか?
「これを習慣にします!」と口に出したり、SNSに目標を書いたりする人は多いと思うのですが、これをしてしまうとむしろ実際の行動が伴わなくなるという経験則です。
これは研究結果としてもあるもので、1920年代から心理学の研究で明らかになっていると言われています。
なぜ公言すると実際の行動が伴わなくなるか?
理由は、他人に話してしまうと「やった気」になってしまい、その満足感ゆえ、実際に目標を達成しようというモチベーションが上がりづらくなってしまうようです。
公言効果、イメージ満足、なんていう名前もついているみたい。
ゆえに、習慣化をする際には最初のうちは誰にも言わずコツコツと秘密裏にやっていく。
その後に時間がある程度経った時に「実はこんなことをやっていて」と進捗をシェアするくらいがいい。
*
そしてこの経験則は、作家の森博嗣先生がオススメしている「個人研究」の話にも通じると思っています。
森先生は本書の最後の方で「個人研究」への取り組みをススメられています。
勉強の本質的な価値を知るには「個人研究」こそ打ってつけ。
曰く、個人研究とは、本当にどうでも良いこと、小さなこと、誰も目を向けないようなことをテーマにして、徹底的に調べたり、あるいは試したりするものを指します。
いわゆる「研究」とは世の中に存在しない知見を得る行為です。
したがって、既にある知見を学ぶ「勉強」と比べて普通の人にはハードルが高く、ちょっと考えただけで尻込みする人も多いでしょう。
しかし「個人研究」はそこまで本格的なものではなく、趣味に近いものだと考えて良いのだとい言います。
研究は秘密裏に
ここで大事なのは、しばらく人には話さないことである。
あくまでも、自分一人の活動として、日々少しづつ進めるのがよろしい。
記録は残した方が良いけれど、ネットなどでの公開は控えよう。
少なくとも1年か2年は黙って秘密裏に進めることをおすすめする。
何故なら、その沈黙の期間に、あなたはきっと自分だけの「楽しさ」を見つけることができるからだ。
公開すると、たちまち他者を意識したものになるし、また反響があることで、自分の動機が濁ってくるだろう。
人のために、という部分が出てくると、目的を見失うことになりかねない。
まずは自分の楽しみを見つける方が先決で、それが確固たるものになってからならば公開しても大丈夫だと思われる。
*
冒頭の「なぜ私が長めの時間軸で取り入れていくのか?」という話に戻ります。
この理由はいくつかあるのですが一番は、長めの時間軸で取り組んでいかないことには、習慣にはならないし、習慣とは呼べないと思うからです。
そして、その中で特に最初のうちは公言はできる限り控えています。
話の流れでつい言ってしまうこともゼロではないのですが、強く意識して公言するのを控えています。
で、ある程度の時間が経過したあたりでようやく公言をする。
こうすることで「やった気」を抱かないようにしている感じです。
習慣化に取り組む際に「やる気」は注意点として上がりがちだと思います。
やる気に頼っても習慣は作れない。
だから仕組みに頼るようにしましょう、的な話です。
実際私もこれには明確に同意します。
しかし思うのは、「やる気」と同じくらい「やった気」も習慣化においては注意点として話題に上がっていいのではないかということ。
なかなかに「やった気」は手強い。
つい公言したくなってしまうのも人間ですし。
いかにして自分に「やった気」を抱かせないか。
これは習慣化において結構大事なことなんじゃないかなと思っています。
UnsplashのNataliya Smirnovaが撮影した写真
【著者プロフィール】
著者:田中 新吾
ハグルマニ代表。お客様のビジネスやプロジェクトを推進する良き「歯車」になる。がミッション。命名屋(命名総研)、タスクシュート認定トレーナー、栢の木まつり実行委員会事務局長(https://kayanokimatsuri.com) 、RANGER管理人(https://ranger.blog)としても活動中。
●X(旧Twitter)田中新吾
●note 田中新吾









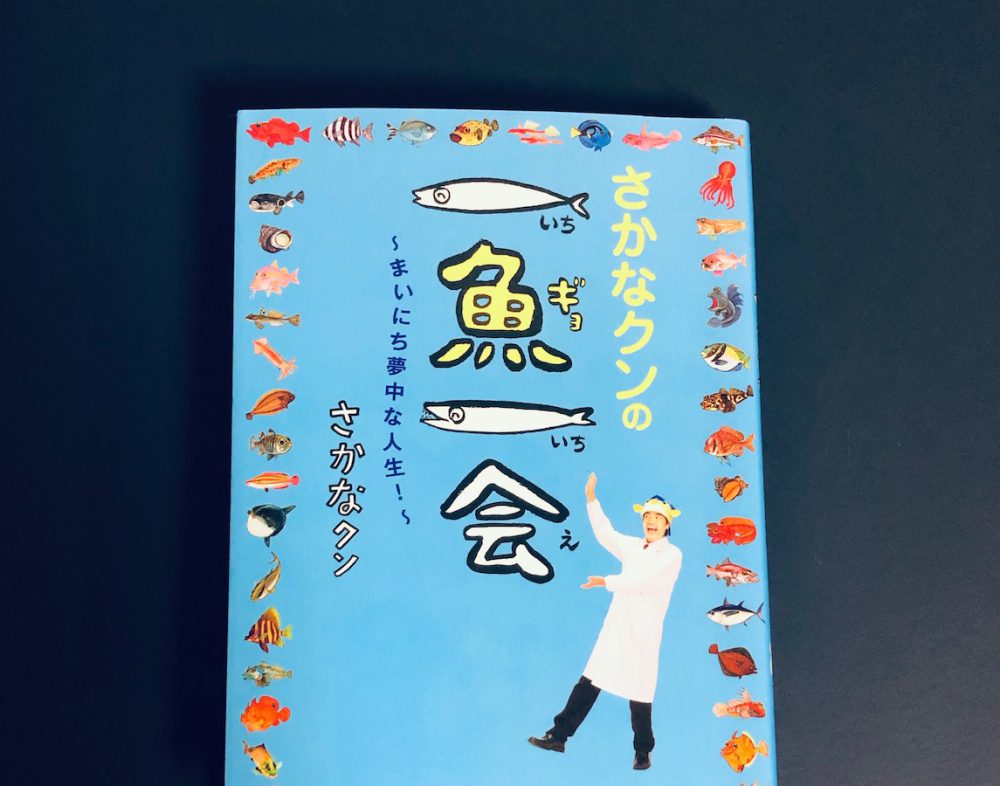

コメントを残す