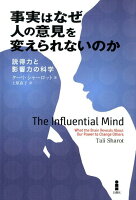「今日はどれほど他人の真似をすることができたか?」を毎日のチェック項目にしているという話。
「今日はどれほど他人の真似をすることができたか?」
これは私が日々のチェック項目として使っている項目のうち、かなり気に入っているものの一つである。
そして、その日にすることができた他人の真似のバリエーションが多いほどその日の豊かさを感じている。
今日はどれほど他人の真似をすることができたか。どんな他人の真似をすることができたか。ここは今の自分にとって大事なチェックポイント。
— 田中新吾|ハグルマニ (@tanashin115) June 5, 2024
今回はこのチェック項目ついて補足も兼ねて考えていることを書いてみたい。
*
そもそも、私が「他人の真似をする」ようになったのはどうしてかについてから。
この起源は自分の中では明白で、大学受験の頃から学生時代までお世話になった塾長の影響がかなりの部分で大きい。
塾長の「自分の考えなんてない、所詮、色んな考え方の集合体」「だから人の考え方はどんどん真似をする」という考え方に強い影響を受けたのだ。
この話、最初聞いた時は「自分の考えなんてない」ということついて不思議に思えてならなかったのだが、今となれば当時の塾長の言わんとしていたこともよく分かる。
そして、社会人として仕事をするようになった私が特に意識していたこともこれだった。
高い成果を上げている人を見つけ、その人の真似をする。
仕事について何にも知らなかった私がやれることはただこれだけだった。
多くの成果(社内MVPをはじめとした数々の受賞など)に結びついていたのは何を隠そう、このできる人の真似の実践によるものだったとしか思えない。
*
そして時を経て、2019年頃に出会い、読んだ2つの本に影響を受け「他人の真似をする」という私の考え方はより強固なものへと変わる。
まず一つ目が「事実はなぜ人の意見を変えられないのか」。
もう一つ目が「自分を捨てる仕事術」である。
それぞれ見ていきたい。
「事実はなぜ人の意見を変えられないのか」の中で私にとって大きな発見となったのは、「社会的学習」という元来人間が備える能力の話だった。
著者であるターリー・シャーロットは本の中で次のように述べている。
人間の脳は、社会との関わりの中から知識を獲得するように設計されている。
最も価値のある商品の見分け方から、ミカンの皮の剥き方に至るまで、ほぼすべての事柄を他人の行動を観察することによって学んでいるのだ。
模倣し、吸収し、採用するという一連の作業を、私たちは意識せず行うことが多い。
こうした仕組みの利点は、その環境における自分自身の限られた経験からだけでなく、多くの人々の経験から得られた情報や技術を拝借できるところにある。
要するに、ほとんど無意識だから気づきにくいだけで、「人は生まれながらにして周囲の人から学ぶ性質を身につけている」ということなのだ。
これを受け、
「いやいや私はそんなことはない」
「私は普通の人よりも影響を受けにくい」
と主張する人も中にはいるかもしれない。
しかし、ターリー・シャーロットは統計から考えてもそれは無理な話だと述べ、したのようにその仕組みを説明する。
実際に多くの人が、自分は他とは異なる存在でありたいと願っている。
自分が他人の好みによって形成されていると考えるのは不愉快なのだ。
個性的でありたいという意識的な思いは、無意識的な社会的学習能力と相まって、私たちの目を同じ「個性的な」選択肢へと向けさせる。
結局、「個性的でありたい」と願う意識が、そもそも私たちに備わっている「社会的学習」への理解を妨げているだけなのだ。
私たちは生まれた時から「社会的学習」によって、常に誰かから真似るようにプログラムが埋め込まれている。
そして、どうあがいたとしてもこの仕組みが備わっている生き物である以上、「所詮、色んな考え方の集合体」であることからは誰も脱出することはできないのだ。
したがって、ものまね芸人生活40年、現在のネタ数は500人、現在も進化し続けるものまね界のレジェンドコロッケ氏は、「マネることは人生そのもの」だというが、これは真に慧眼と言える。
*
そして2つ目が自分を捨てる仕事術。
これはスタジオジブリの鈴木敏夫さんのお弟子さんである石井朋彦さんが書いた著書だ。
石井さんが鈴木敏夫さんから教わった自分を捨てる仕事術を学ぶことができる。
端的に言うと「自分なんていない、自分は捨てるんだ」という考え方に則り仕事を行うというもの。
この本に初めて目を通した時、私は遥かに大きな衝撃を受けたのを今でも覚えている。
なぜか?
それは冒頭の塾長が言っていたことと同じようなことを言っている人をこの本で発見し、尚且つその考え方で大きな成果を上げていたからである。
*
経験的に、他人の真似をすることには多くの利点がある。
そしてそれを妨げているのはただ一つ「自分という存在」でしかない。
去る5月25日のセミナーの講義で使用したスライドが「見やすい」「分かりやすい」と評判だった。
このスライドが生まれたのも結局のところこれまで様々な人のプレゼンテーションやスライドを見て、良いところを真似してきたからで、自分の中から生まれたものでは決してない。
昨年頃から新たに真似をする対象として加えたものがある。
勘の言い方はお気づきかと思うが、そう「AI」だ。
「結局自分で考えた方がクオリティの高いものができる」などとたかを括っている人と「自分よりも圧倒的にクオリティと生産性の高いAIのアウトプットをいかに真似るか」と考えている人がいた場合に、どちらの方が長期的に成長するだろうか?
私が思うのは後者だ。
であるから、もう早々にAIとの勝負を止めた。
今は、AIを自分よりも圧倒的に能力が高く、それでいていくらでも働くことができる存在として認め、そんなAIからさえもどう真似ていくか、そんなことを考えている。
真似する対象の他人にAIも含まれた、そんな具合だ。
今回書きたかったことはこんなところである。
「今日はどれほど他人の真似をすることができたか?」
を日々のチェック項目にこれからもますます誰かの真似をしていきたい。
UnsplashのUgur Akdemirが撮影した写真
【著者プロフィールと一言】
著者:田中 新吾
ストレングスファインダーの1位が学習欲なので、幾つになっても他者から真似ぶには貪欲に行きたいと思ってます。
ハグルマニ代表。お客様のビジネスやプロジェクトを推進する良き「歯車」になる。がミッション。命名士(命名総研)、タスクシュート認定トレーナー、栢の木まつり実行委員会事務局長(https://kayanokimatsuri.com) 、RANGER管理人(https://ranger.blog)としても活動中。
●X(旧Twitter)田中新吾
●note 田中新吾
会員登録していただいた方に、毎週金曜日にメールマガジン(無料)をお届けしております。
「今週のコラム」など「メールマガジン限定のコンテンツ」もありますのでぜひご登録ください。
▶︎過去のコラム例
・週に1回の長距離走ではなく、毎日短い距離を走ることにある利点
・昔の時間の使い方を再利用できる場合、時間の質を大きく変えることができる
・医師・中村哲先生の命日に思い返した「座右の銘」について
メールマガジンの登録はコチラから。
最後まで読んでくださりありがとうございます。
これからもRANGERをどうぞご贔屓に。