バラけるか?同調するか?「変」というものについて考える。
少し前に、若者からこんな投げかけをされた。
「どうして犯罪はなくならないんですかねえ?」
最近の悲しい事件が目に留まったらしい。
大人ならば若者に何かしら有意義な回答をしてあげるべき、というのがこれまで学んだ常識なのだが、こんな根本的?でシンプルな質問が逆に難しい。
咄嗟に閃いたのが「種の仕業」として処理することだった。
いろいろと問題のある人間ではあるが、ここまで繁栄してきた人間というのはやはり好きか嫌いかは別にしてやはり凄くって、その人間種をもう少しリスペクトしたほうがいいのではないか?
そして、そうした方が少しは楽になるのではないか?そんなことをここ数年考えるようになったから浮かんだんだと思う。
それでも、残念ながら自分が逃げの一手しか返せないことを苦々しく感じ始める。
そしてまた、こんな回答が真っ先に出てくるような大人はかなりの少数派だろうから、変り者で申し訳ないような気もする。
今回は「変」というものを考えた話である。
種の問題
「種の仕業」とは、生物の種はその性質がよりバラけるようにできている、というものだ。
種の性質が一様になってしまうと、同時期の同じ環境変化に順応できずに総倒れしてしまうリスクがある。
一様では絶滅の恐れがあるのだ。
だから、性質がバラけるように産み落とされる。
暑さに強い人と寒さに強い人がいる、といったように・・・。
性質に、頭がとんでもなく良かったり、野球がすこぶる上手かったり、と様々のものがあるように、犯罪でいうと、「あなたがひどい!」と思えることがひどいと感じずらい、とか、直情的で思い込んだら止められない、とか、その後のことを考えない、とか、いろいろなものがあるのだろう。
種は生きのびるために常に模索していて、時に今でいうところの犯罪を起こす方が生き延びるのに有利であるという判断によって、あるいはそんな冷静な場合ばかりではなくて、ここで犯罪を起こさないと自分の身が危険である、というような直感によるケースもある。
法にも、そしてその取り締まりにも抜け道があるから、罪を免れられると判断して選択する場合もあるのだろう。
そしてその瞬発力や見立てが、時代や環境によっては生きるために有利になることだってある。
ずーっと今のルール(憲法や法律)にしたがった社会が続いて、犯罪をしないように生きる方が有利だと学習できれば犯罪は減るように思うが、過去の記憶が遺伝子に刻まれていて、それぞれのスピードで変化していくののが実際なのではないだろうか。
環境の変化より順応の方に時間がかかって、今の時代の環境にたまたまアンマッチなまま残っている種が存在するのだ、という風に私は理解する。
そして、順応のための学習は種や環境の違いによっては数百年単位かかったりする場合もあるんではないだろうか・・・。
順応に時間がかかるのは、敢えて変化しない種を残すことが種全体としてのリスクヘッジをしているようにも感じる。
種は、緊急時に犯罪を犯してまで自分の身を守ること(現代の正当防衛)が有利である社会にもどこかベット(賭け)して備えているのではないか、と。
さらには、他の種の耐性を維持するためにある種危険な種を紛れ込ませているのではないか?とすら感じる。
このように種はバラけるようとしているから、そのバラつきが犯罪の出現に影響していて犯罪はなくならない、というところに至る。
私のこんなような回答は、結局若者に
「変な人がいるけれど人はなかなか変わらないものだから、犯罪がなくなることに期待しなさんな。」
と言っているようなもので、これでは気休めにしかならない・・・。(気休めが全く無意味ということではないのだろうが・・・)
いい大人がこの程度しか言えない。
これが逃げの一手という意味合いで、若者が何とか具体的に犯罪を減らす方法はないものか?というニュアンスだったならば、全く響かないものだったのだろうと思う。
犯罪を減らす方法は、人によっては数百年かかる順応をどうやって短縮するか?いわゆる学習にその可能性はあると思うのだが、とても私ごときが語れるものではないように思えてそこから逃げた回答しかできなかったのだ。
「面白い」=「変」
この苦々しい私の回答に対して、若者の反応は「面白い」だった。
そう言えば、最近他でも周りから「面白い」と言われることがあって、若い頃からずっと「面白い」などと言われたことはなかったから、これには少し戸惑っている。
若い時分はそう言われるとすぐに有頂天になったのだろうと思うのだが、今の私はこの「面白い」を好意的な意味に捉えることをしなくなった。
それは、気を使ってくれただけで何事にも「面白い」には「変だ!」が含まれているものだから。
そう、単に「変」なだけなのだ。
万が一、その変に共感する部分がある場合に「面白い」という言葉にやっと好意的な意味が含まれるという類のものだろう。
人の「変」には必ず相手の不快が含まれていて、それを排除しようという同調圧力がいつだって働くのが自然なこと。
「面白い」という言葉を聞いた時、多くの場合は自制しなさい、というサインだと理解するようになった。
視点を変えて、種の話を私自身に当てはめてみる。
種にはバラけようとする力が備わっているが、逆の同調しようとする力も備わっている。
今度は種全体がバラけることでリスクヘッジしているのとはちょっと毛色が違うが、周りに同調することがその1つの種が生きるのに有利に働く。
周りに同調しないと命を奪われるなんてことは今でも割りと起こることのように感じる。
種は、この正反対のものを同時に持ち合わせているというのはここまで人間を見てきて納得できる話だ。
では私の場合は、このバラけようとする力と同調しようとする力のどちらが強く出ていただろうか?
バラけようとする力が強い人は、子供の頃から人と違うことをしたくてしようがないものだ、と聞く。
確かにそんな個性的な友達がいた。
私はその個性的な友達をどこか羨ましげにそれでも迷惑げに眺めていたように思う。
私の場合違うことをしたくてしようがない、という気持ちはどうやらそこまでではなかったから、同調の方が強く出ていたというところなのだろう、と思う。
バラける、を担う種と同調を担う種がいるように思う。
そんな私に「変」が出るようになったのはなぜだろうか?
今になって、バラけようとする力が動き始めたということだろうか?
それともかなり時間はかかったが学習して変わろうとしている、と見るべきなのだろうか?
いや、単に年をとって自由時間が増えて頑固になってきただけと見るべきだろうか?
同調は停滞、バラけるは進化
どんな見え方であってもどれもが正しいと言っていいのだろう。
そして、どれだけ意味付けしようとも、そして、どれだけ自分の力で変化してきたように感じたとしても、それは所詮種に最初から備わったものでしかないのかもしれない。
ただ意味づけついでに言っておくと、「変」になった理由は簡単と言えば簡単なことだ。
ちょっとだけ自分で考えた、ということなのだ。
世の中で言われている「答え」を上手く拾ってくれば「変」とはなりづらい。
これが私がここまでずーっとやってきた効率的合理的なやり口だ。
ところが、ちょっと面倒でも自分で考えてみると・・・。
自分ごときが考えの主体となるのだからそこに間違いなく「変」が生まれる。笑。
専門家の言葉の引用でないと概ね「変」だと言われてしまう。汗。
そして「変」には今回の苦々しい逃げの一手のようなとんでもなく不完全な「変」もある。汗。
「変」は迷惑なものだ。
それでも「変」に進んでしまっている自分がいる。
何とか「変」に進む自分を勇気づけられないものだろうか?
そう言えば、「みんなが賛成する案は失敗する」と言われたのはもうずいぶん前のことになる。
確か取締役会で多数決で決めたものは上手くいかないという話だったと記憶している。
少数意見の中に未来を開くものがある、と言われるようになった。
意見がバラけて出てきた新しい発想はいつだって「変」なのだから、バラけない同調は停滞である、とも言える。
私はこのような意味づけに力を得て、これからは自分で考えて「変」でありたいと思う。
種の導きによって身体がいうことを聞かず・・・笑、どうやら「変」を量産するつもりのようなのだ。汗。
迷惑な話だ。
ましてや、不快なだけの「変」をまき散らすのはなおさらのこと。
だから周りにとって好意的な面白い、が少しでも含まれている「変」でありたい。
ありたい、とできるでは全く違うのだが・・・。
危ういので、この「変」を量産する危険分子への注意喚起として、最低限心得なければならない言葉を胸に刻んで終わることにする。
人はアホなことをする権利、他人を愛する権利、他人をバカにする権利などを持つが、他人に愛される権利とか、他人に褒めてもらう権利とか、他人に理解してもらう権利などはない。
(中略)
他人に理解を求めるのはあなたの自由だが、他人に理解してもらうのはあなたの権利ではない。
当然ながら、自分の「変」を他人に聞いてもらうにしても、理解を強要してはならないのだ。
はい、心得ました!
では大変つたないのですがとりあえず、「変」を話した最後に、
「極端なことを言いました」
「忘れてください」
「変わり者なんです」
「知らんけど・・・(大阪の素敵な言葉)」
などの締めの緩衝ワードをしっかりと用意しておくことにしよう。
とにかく、自分で考えて、その「変」に(本人は変だと思っていないからまた厄介なのだが)自分で納得できればそれで十分。
ひとつの種としては、「変」を考えただけで種全体のリスクヘッジのための役割は担っていることになるのだ、と私は決めた。
これも明らかに「変」な決め事なのだが・・・。汗。
UnsplashのRobert Gourleyが撮影した写真
【著者プロフィール】
RYO SASAKI
工学部を卒業後、広告関連企業(2社)に29年在籍。 法人顧客を対象にした事業にて、新規事業の立ち上げから事業の撤退を多数経験する。
現在は自営業の他、NPO法人の運営サポートなどを行っている。
ブログ「日々是湧日」
「変」をバラまきたいのではなくて、自分で考えることが大切だと言いたかったのですが、伝わりましたかどうか・・・。
会員登録していただいた方に、毎週金曜日にメールマガジン(無料)をお届けしております。
「今週のコラム」など「メールマガジン限定のコンテンツ」もありますのでぜひご登録ください。
▶︎過去のコラム例
・週に1回の長距離走ではなく、毎日短い距離を走ることにある利点
・昔の時間の使い方を再利用できる場合、時間の質を大きく変えることができる
・医師・中村哲先生の命日に思い返した「座右の銘」について
メールマガジンの登録はコチラから。
最後まで読んでくださりありがとうございます。
これからもRANGERをどうぞご贔屓に。







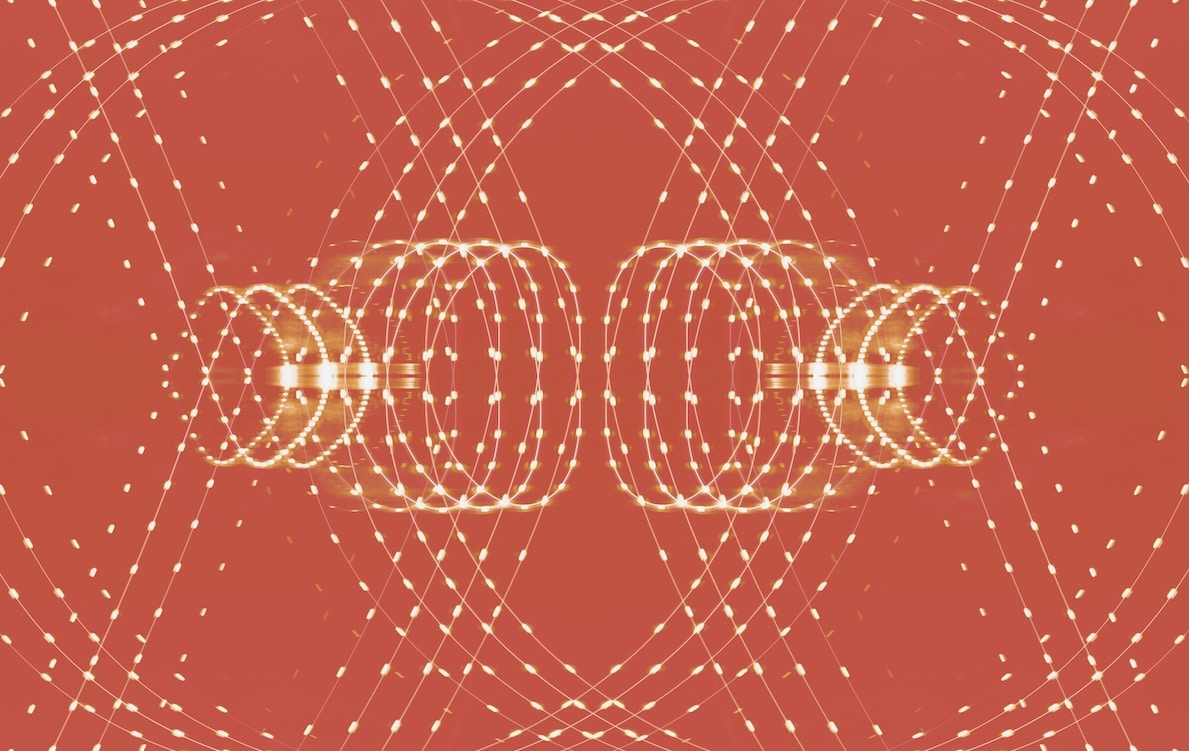



コメントを残す