「情報の非対称性」を解消する方法、それはあらゆるものを疑って自力で紐解くことだ。
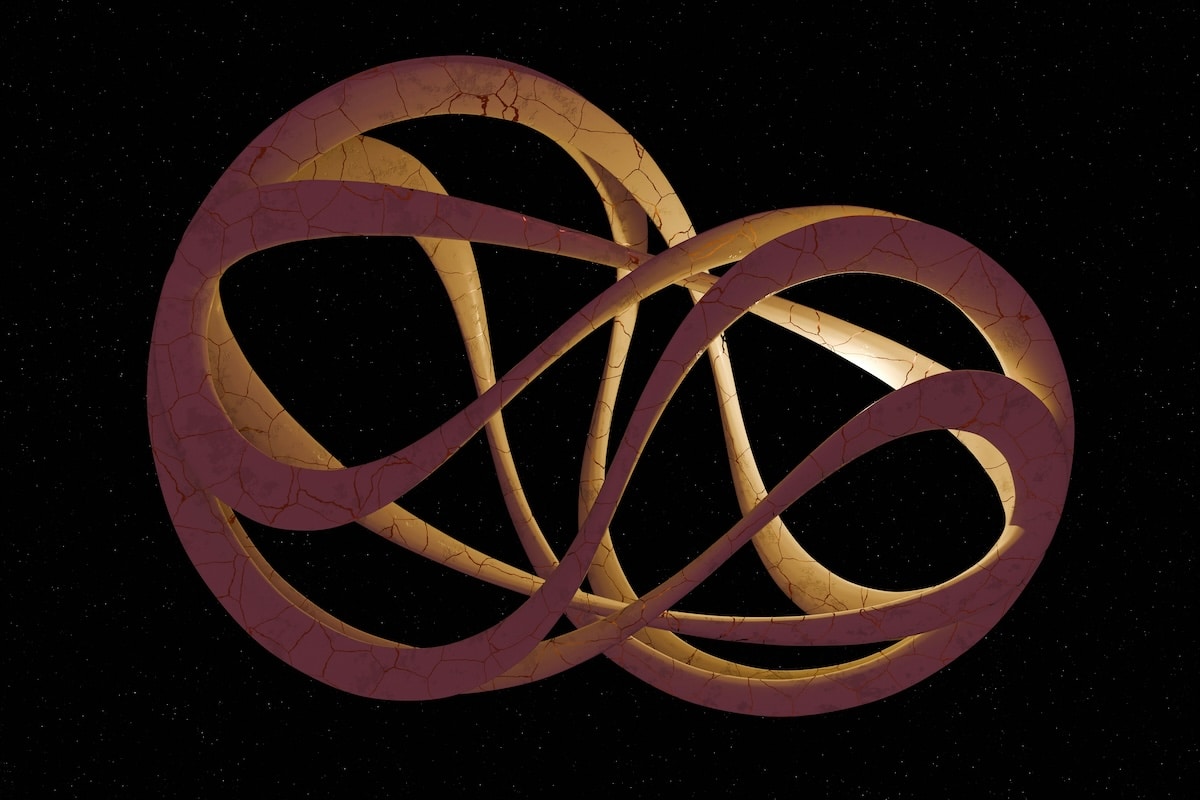
ネットCMに掃除機が頻繁に出てくる。
私のベテラン掃除機の吸引力が落ちたように感じたので、ネット検索したのだった。
何べんも同じCMを見せらされて、
「お使いの掃除機、吸引力落ちてきてませんか?この商品は吸引力が落ちません。」
この宣伝文句が耳について離れないようになってしまった。
繰り返し見ることで買ってしまう効果のことを「ザイオンス効果」と言うらしいが、私は繰り返し見せられることで、むしろ少しイラっとしてしまって、逆にこの文句を疑いの目で見るようになった。笑。
掃除機のように、私の興味ある物ならばまだしも、全く興味のない物を繰り返し見せられるのは苦痛でしかない。
その苦痛はCMによってよく起こることだから、しょっちゅう無にならないと(何も感じないスルースキルで)いけない。
購入検討者を何とかその気にさせようとするのがマーケティングというものだが、これに対して購入検討者はいつも戦っているのだ!
そんな被害を訴えてみるも、これは言ってしまえば現代の日常であることをあらためて感じた。
今回は、これをキッカケにして『情報の非対称性』というものにあらためて思いを巡らせることになった。
掃除機を紐解く
「お使いの掃除機、吸引力落ちてきてませんか?この商品は吸引力が落ちません。」
こちらは某コードレス掃除機の宣伝文句である。
この宣伝文句をあらためて眺めると、強い吸引力で長く使える商品であると、認識してしまうようにできている。
認識してしまう、という言葉を使ったのは、私調べで、以下のことがわかったからだ。
・コードレス掃除機は、一般的にコード式掃除機に比較して吸引力が弱い。(昔よりは吸引力がアップしたが・・・)
・吸引力は落ちる前に、バッテリーの寿命が先にやってくるので、コードレス掃除機は一般的にコード式掃除機に比較して、寿命が短い。
コード式掃除機に比較すると吸引力も強くないし、寿命も長くないということのようだ。
先ほどの宣伝文句にウソはないのだが、宣伝文句には言ってないことがたくさんある。
言っていないのは=裏に巧みに隠れているのは、コード式掃除機との比較だった。
多くの人は、コードレスというのはそもそもそんなもんだろう、と理解しているのかもしれないが、私に限っては、コードレス掃除機の利便性、あるいはメーカーのブランドイメージなどに引き寄せられて、見えないままに決断してしまうところだった。
もちろん吸引力が気にならない人であれば、逆に見えない方が いいのだろうけど・・・。
簡単に勘違いしてしまうからなのか、このような短いCMにも『情報の非対称性』というものが潜んでいるんではないだろうか?
私はそう思ってまた身構えるのだ。
情報の非対称性
『情報の非対称性』とは・・・
利害関係のある当事者間で保有する情報に格差がある状況を指します。
経済学のみならず、幅広い分野でその存在が認識されています。
『情報の非対称性』の例
商品やサービスの売り手と買い手の間企業と投資家など異なる経済主体の間
金融市場での資金の貸し手と借り手の信用情報
情報をない方が、情報を持っている方に騙されたりするようなことがある。
『情報の非対称性』という言葉が出てきて、そのことがそういった概念が理解され、みんなが問題として共通認識するようになった。
問題と認識されることで、改善に向けてスタートラインにやっと立てるものだ。
はたして、今後この問題はどこまで改善されるのか?
ーーーーーーーー
『情報の非対称性』を持ち出して、この掃除機のCMをやり玉に上げたいわけではない。
CMは短い時間だからメリットしか伝えられない。
そして、実際に吸引力の比較はネットには上がっていて、調べることができたわけだし・・・。
(吸引力が非公表のコードレス掃除機もあるにはあるが。)
CMは、ウソは言えないが時間が短いから、鼻っからメリットしか言わないようにできているものだ。
あらためて言うほどのことではない。
それでもこのことから思うのは、すべての情報伝達というものに時間の制約があって、時間の制約があるということは情報を意図的に選択せざるをえないということになる。
意図的な選択がされれば、多かれ少なかれ情報格差は起こるわけだ。
だから、企業と消費者、政府と国民、親と子供、先輩と後輩など、あらゆるところに情報格差が都度発生して当たり前、と理解した方がいい、ということが言えることになるのではないか?
企業の営業担当が、商品のマイナス情報ばかりを選択して伝達したとしたら、売れやしない。
だから、生きるためにそんな情報の選択はできない。
また、社会には、相手をコントロールしないと存在し得ないとなっている人や地位や組織があって、そこにおいては、相手をコントロールするために、意図的な情報選択をせざるをえないのだ。
こんな風にして眺めると、『情報の非対称性』というものは必然として存在していて、なくなることはない、と確信せざるを得ない。
疑って自力で解く
『情報の非対称性』については規制する法なども一部あるが、様々なレベルのものがあるから、法規制にも限度がある。
そんな中、なくならない『情報の非対称性』にどう向き合えばよいものだろうか?
・・・自力で解消するしかない。
自力で解消するためのヒントはないか?
掃除機について私が自力で解けた(解けたと思えているだけかもだが・・・)のはなぜだったのか?
それは、宣伝文句を疑ったことに始まる。
すべてに裏があることにやっと馴染んできたから、と言ったらいいのか・・・・。
人に対して疑うことは悪いことだ、という昔からの刷り込みが自分にあった、ということを言葉にできたのが、わずか数年前になる。
疑う=悪い人、か、疑わない=良い人、の2択。
これが単純過ぎたのだ。
「裏を見るな!」
「裏を読むな、いやらしい!」
と言われた。
これも周りが自分をコントロールする言葉だった。
今は、裏を読まないわけにはいかない。笑。
世の中には、相手を騙そうとする悪い人もいるが、全くそんなつもりもない人の方が多い。
そんな人からの情報だって、まずは時間制約があり、そしてそもそもの情報不足によって、騙されることがあるのだ。
そう考えるとすべての人、すべての情報を疑い、裏を読むべき、ということに至る。
「疑いっ放しの人生なんてものはシンドイ」そんな感覚はもはや過去のものだ。
疑うからといって悪い人が社会に増えたわけではない。
ことさら社会に対して恐怖を感じることはない。
社会がそれだけ複雑になった(本来の複雑さが見えてきただけ?)のだ。
疑うは大人としての当然のたしなみレベルのものだから、疑うをもっといいイメージの言葉に転換しないとならない。
これは口にしないだけで、みんながわかっていることなのかもしれない。
そんな当たり前のこと、これに私は今更ながら気づいた。汗。
すべての情報を疑って、自分で裏を調査して、自力で紐解く。
自分でコントロールできる範囲が広がれば、世の中に恐怖を感じること、世の中を恨むこと、同時に世の中に依存することのどらもが薄まり、自分が健康にもなるから。
これは強がってキレイごとを言っているだけなのかもしれないが。汗。
・・・・・・
ところで、掃除機の買い替えの件だが、今回コードレス掃除機の裏を紐解いた?ことで上機嫌になった私は、それで満足して買い換える気がすっかりどこかへいってしまったようで・・・。
どうやら紐解くことが楽しいらしい。笑。
紐解くことで満足ならば、それをしていけば人生どう見ても幸せ。
材料となる『情報の非対称性』はそこら中にあるから、楽しみにはことかかない・・・笑。
『情報の非対称性』を楽しんでいこう!
いくら私が変わり者だとしても、これはさすがに言い過ぎかもしれない。
UnsplashのSteve Johnsonが撮影した写真
【著者プロフィール】
RYO SASAKI
世の中はすべて重なり合った状態。
それを確定してはほどいて、確定してはほどいて・・・そのかりそめの連続なのかもしれません。
工学部を卒業後、広告関連企業(2社)に29年在籍。 法人顧客を対象にした事業にて、新規事業の立ち上げから事業の撤退を多数経験する。
現在は自営業の他、NPO法人の運営サポートなどを行っている。
ブログ「日々是湧日」







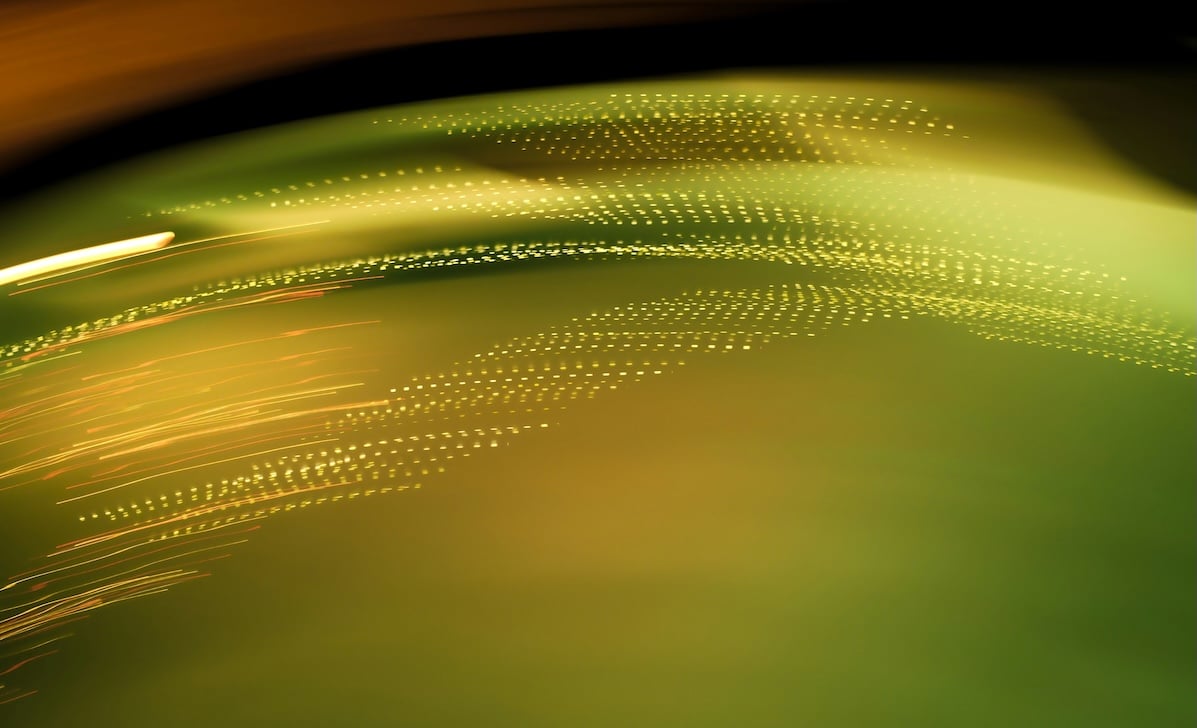


コメントを残す