メンバー間で共有可能な「そうであったら本当に素晴らしいと思える景色」を、「見立てる」ことができると、プロジェクトはとてもスムーズに動くようになる。
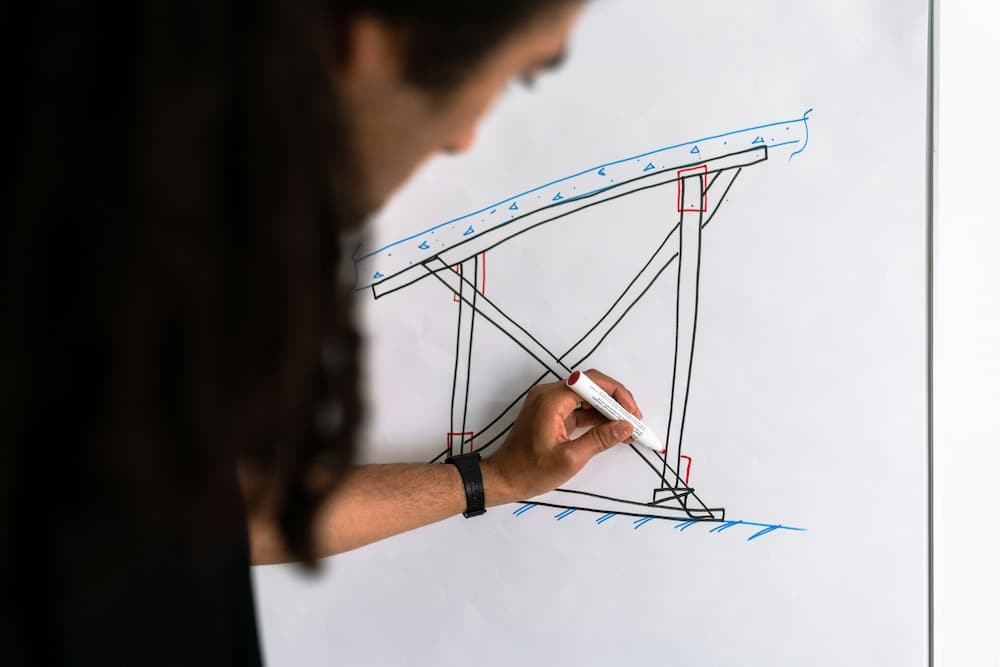
昨年の中頃に以下のような投稿をXにしました。
プロジェクトを進める時に大事にしている考え方。
— 田中 新吾 (@tanashin115) August 17, 2024
・やってみて修正する
・定期的に欠かさず少しづつ進める
・現在できることに集中する
・今の積み上げで一手先の見通しを立てる
・ネーミングやコンセプトの持つ力を上手く使う
・メンバーが共有できる景色を作る
・臨機応変に進める…
今年はここに書いた経験則や知見について、一つづつ内容を掘り下げていきたいなと思っています。
今回は「メンバーが共有できる景色を作る」をピックアップしました。
この考え方はXを投稿した時からブラッシュアップされていまして、
現時点では、
メンバー間で共有可能な「そうであったら本当に素晴らしいと思える景色」を、「見立てる」こと
としています。
そうであったら本当に素晴らしいと思える景色
これが共有されるプロジェクトと、されないプロジェクトでは最終的なクオリティが随分違うなと思っています。
一体なぜなのか?
この疑問に対してのヒントが一つ、2022年5月22日に読んだ以下の本に書かれていました。
本書によれば「ビジョンの機能」は3つあります。
- 共有された目標となる
- 日々のモチベーションの源泉となる
- 行動と判断の基準になる
そして、私が考える「景色」についても、ここでいう「ビジョン」と同様の機能があるなと思いました。
さらに、
そうであったら本当に素晴らしい、と思えるものだけがビジョンを名乗る資格を得ることができる。
そうであってこそ目標になり、モチベーションの源泉となり、行動や判断の基準という、三つの機能がちゃんと働いてくれる。
とも書かれており、この点も自分の考えを磨くのに大変参考になりました。
本書によれば、上の三つの機能が正常に働いているということは、「そうであったら本当に素晴らしいと思える未来像=ビジョン」になっているということ。
しかし、私は「そうであったら本当に素晴らしいと思える未来像=ビジョンを作る」ではなく、「そうであったら本当に素晴らしいと思える景色を見立てる」という言葉を用いた考え方としています。
これには明確に理由がある。
端的に言えば、ビジョンという言葉には「理想の将来像」という意味合いが強すぎるのですよね。
そして遠い将来にあるビジョンに向かって、今この時を手段にしてしまいがち。
要するにビジョンというのは「トップダウン思考」なんです。
この状況というのは経験的に、今この時に真に心血を注ぎにくい。
ではこれに対して「景色を見立てる」とは一体どういうことか?
私がこのフレーズを用いるようになったのは以下の本を読んでからでした。
こちらは2023年7月読んだものです。
以下、刺さりに刺さった箇所の引用です。
「見立て」は、文芸や華道、茶道などの芸術、歌舞伎、能などの伝統芸能だけでなく、デザイン、マーケティング、映像表現、そして日々の暮らしの中でも生活文化を豊かにする認知的手法として用いられてきた。
重要なのは、それが「未来」の先取りでも、「過去」への回帰でもなく、目の前の現実が新たな「景色」として立ち現れることにある。
目の前の現実そのものに、新たな意味や可能性を見出すことが「見立て」なのである。
新たな「景色」を共有する人たちの間には「ともに居る」という感覚が芽生え、その感覚自体が場の魅力や価値を高めていく。
そこには、祝祭感やライブ感が生まれていく。
多様な背景を持つ人たちが一つの風景を見ることができれば、多様でありながら共通性のある集団が生まれるのである。
いかがでしょうか?
本書で「景色」とは、目の前の現実に、新たな意味や可能性を見出すこと、つまり見立てることで立ち現れるものとされています。
この「景色」と「見立てる」の解釈が非常にしっくりきたのです。
つまり、景色は今目の前にある現実が土台となって生まれるものであるため、少し先のことで未来の状況を指す概念ではあるものの、「目の前の現実から地続きだからこそ、輪郭が見えるちょっと先の未来」ということだと理解しました。
だからこそメンバー同士で共有できるのだろうなと。
ビジョンにはこれがなかなか難しいのではないか?と思うわけです。
だいぶ遠い将来像のことであるため、今目の前にある現実の地続きになっていないように思えてしまう。
ゆえにその像はぼんやりとしていて、輪郭も朧げでなんだかよくわからない状況になってしまうという。
かなり前に「曖昧さは人を動けなくする」という記事を書きましたが、まさにこれです。
よく分からないぼんやりとしている将来像ではなかなか人は動くことができないのだろうなと。
「ビジョン」がトップダウン思考だったのに対して、ここでいう「景色」は「ボトムアップ思考」と言ってもいいでしょう。
ここで一つ具体例を。
昨年地元のメンバーと立ち上げた「栢の木まつり」というお祭りはまさにこの
メンバー間で共有可能な「そうであったら本当に素晴らしいと思える景色」を見立てること
をした事例になりそうだなと思っています。
ここでの風景は、
観音堂の境内を拠点にして、地域内で、新旧住民の交流がたくさん行われている状況
です。
実際に何度も訪れたことがある境内、自分が住んでいる地域。
この現実そのものに新たな意味や可能性を見出しました。
そして、その状況に対して皆がそうであったら本当に素晴らしいと思えた。
だからこそ、プロジェクトメンバー全員で共有することができ、もっと言えば関わってくださる様々な方々にも共有することができたのだと思うのです。
世の中ではビジョンが機能する場合も当然あるのだろうなと思いつつ、
(フォアキャスティング思考な)私にとっては「景色」と「見立てる」がしっくりくるのと、それによって上手くいっている感覚もあるため、当面はこの考え方を推奨していきたいと思う次第です。
参照:「世の中には2種類の人間がいる」という話をふと思い出した件について。
メンバー間で共有可能な「そうであったら本当に素晴らしいと思える景色」を「見立てること」を強く意識して、引き続きトライしていきます。
今回の話が何かの参考になれば嬉しいです。
UnsplashのThisisEngineeringが撮影した写真
【著者プロフィール】
著者:田中 新吾
メンバー間で共有可能な「そうであったら本当に素晴らしいと思える景色」を見立てることができた時、いい「外交」も生まれるという実感もあります。
ハグルマニ代表。お客様のビジネスやプロジェクトを推進する良き「歯車」になる。がミッション。お名前プロデューサー、タスクシュート認定トレーナー、#栢の木まつり 実行委員会事務局長としても活動をしています。
●X(旧Twitter)田中新吾
●note 田中新吾












コメントを残す