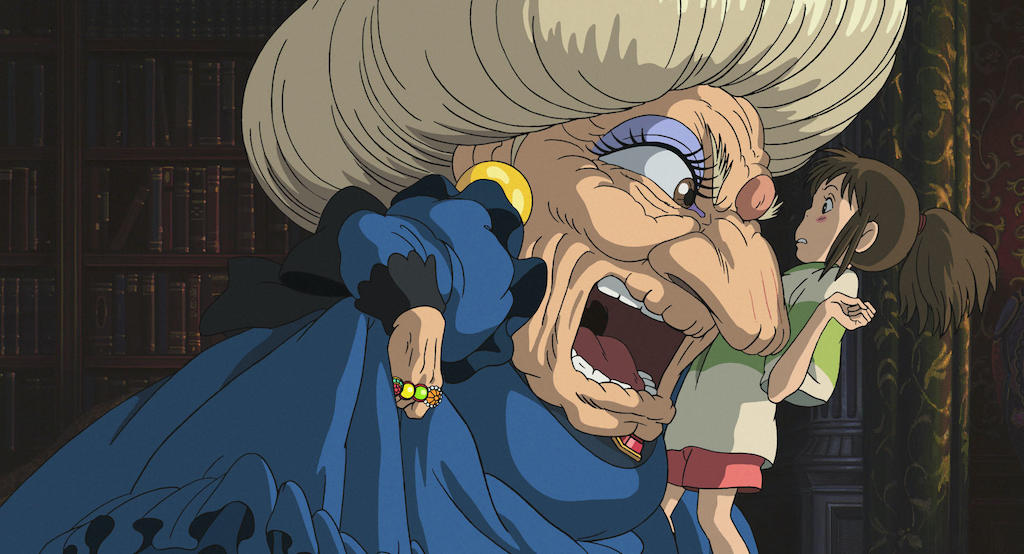「夏目漱石の視点」で現代をながめてみる。

小説家 夏目漱石との接点は、中学生の頃に「我輩は猫である」や「坊っちゃん」を推奨図書として読んだくらいしかなかった。
今となっては、その時の感動どころか、何某かの印象すらもなくなってしまっている。
かろうじて、「細かく観察する神経質な人だ」という思いが残っているくらいだ。
当時は”完読”が「宿題をこなす」ことだったので、それだけしか見えてなかったのだろう。
あるいは、文章の意味を理解することが精一杯で、読む訓練の範疇に留まったのかもしれない。
後から、彼への評が、そのシニカルさにある、とも聞いたが、当時はまだシニカルさというものがわからなかった。
子供の頃は相手への配慮がまだ十分育っていないから、逆にシニカルな目線は当たり前のところもあって、漱石の目線に驚かなかったようにも思う。
そのシニカルさを大人になっても残して、チャンと言葉にできるところはさすがだ、と後からやっと思うに至る。
その当時からもう少しで半世紀が経とうとしているこのタイミングで、意図せずに、再び夏目漱石に出会うことになった。
書籍「私の個人主義」
[itemlink post_id=”8307″]
ここから、3つほど抜粋してみたい。
現代日本の開花
開花とは、人間活力の発現の経路である。
(中略)
現代の日本の開花は前に述べた一般の開花とはどこが違うのか、というのが問題です。
西洋の開花(一般の開花)は内発的であって、日本の現代の開花は外発的である。
(中略)
現代日本の開花が皮相上滑りの開花であるということに帰着するのである。
明治維新の1年後に生まれた漱石は、舶来品がなだれ込むのを観察しながら育ったはずだ。
ナイフやフォークやタバコなどを日本人はみんなが意味もわからずに使うようになった。
言われてみれば確かにという感覚がある。
別に日本人の誰しもが心から使いたかったというよりは一種のブームのようなものだ。
漱石は、海外に留学して体調をこわした、と言われている。
その原因が、外国へのコンプレックスであった。
海外に対しては、たぶん、見る物すべてが珍しくあこがれもあった、と想像もするが、そこを経験しながらもこの開花を、外から押し込まれて”滑稽”のように捉えた。
明治維新の大激流の渦にいる中で、こんな風にある意味冷めた目でというか冷静に眺めた人が他にいただろうか?
今はやっとナイフやフォークが使いづらいことを正直に言えるようになったし、箸でも食べたりするなど、しがらみがなくフラットになったように思う。
新しいものと出会っては、人は踊り、ブームが起こる。
そして時間を経過してフラットなところに落ち着いていく。
私が生きてきた中では、これまでの激変はなかったが、強いて上げれば「バブル期」がそれに当たるのだろうか。
なぜか、仕事の後に乱痴気騒ぎをしないと損だ、というような感覚があった。
私の先輩は投資用の不動産を保有していた。
同期はゴルフ会員権を買い始めた。
ボーナスが上がるし、不動産やゴルフ会員権などの高騰が期待された。
私も雰囲気に呑まれて、唯一、高額のコートを購入した記憶がある。
それでもそのくらいのもので、世の中に疎く、鈍感な田舎者だったからあまり痛手を被らなかったのかもしれない。
みんなディスコで踊った。
投資でお金を増やすために踊った。
お金持ちになった気になって踊った。
真夜中のタクシー乗り場は長蛇の列。
夜中の3時に酔っ払いが1万円札をおでこに当てて、ウォーキングデットのように我先へ我先へとタクシーを求め、さまよっていた。
その時社会がどうなっているのか?自分が何をやっているのか、理解が全くできていない。
力なく、流れに身を任せるしかなかった。
インターネットが出てきた時も「ネットワークの無料提供?」「軍事用?」意味がわからなかった。
その後、世の中はずーっとインターネットに翻弄されることになる。
後からなんとなく大変な時代だったということをながめられるくらいのもので、人はこれからも社会変化に翻弄され続けるのだろう。
漱石のように、ブームの異常性を分離、除外した上で、世の中をフラットに、本質的に捉えることがどこまでできるのだろうか?
道徳と文芸
徳川時代の道徳は(中略)、完全な一種の理想的の型をこしらえて、その型を標準としてその型は吾人の努力の結果実現できるものとして出立したもの。
(中略)
我々ごとき至らぬものも意思の如何、努力の如何によっては、模範通りのことができるんだ、といったような教え方・・・
江戸時代の階級による制約の中の、忠臣、貞女、あるいは腹切などに現れるような一律の道徳感。
これに対して、維新後の道徳感は一律ものではなく、道徳感は低くなったと言わざるを得ない、と漱石は比較して見ていた。
そう言えば、日本人が時代劇を好んで見るのはなぜだろうか?
単純に、勧善懲悪だからなのか?
潔さを見習いたいからなのか?
偉大な武将に対するあこがれなのか?
道徳感が失われた現代からの一時的な逃避なのか?
私は昔からどうも時代劇というものを好んでは見ない。
なぜなのか?明確に考えたこともなかったのだが、漱石によって少しわかったように思う。
当時の道徳をそのまま現代の世界に適用できないから、という感覚、そして、道徳により縛られた世界から解放されたのに、なぜにまた息苦しい社会に戻りたいのか?というような感覚でもあるのだと思う。
そこに、ある種のノスタルジーというかあこがれがあったとしても、江戸時代のように一律の道徳感を追いかけるような社会に戻ることはないだろう。
ここまで生きてきた経験によって、自分は江戸時代の人々のような道徳感の人間になれそうもないことがわかってきた。
できるだけ自由でありたい。
これは紛れもない感覚である。
「昔は良かった、今の道徳は・・・」と言う嘆きを聞いたことがある。
江戸時代の人に照らし合わせた時に現代人(自分)が不道徳を感じることによって、自己肯定感を削がれることを嫌がっているのかもしれない。
道徳心が低くなって、世の中に勝手な振舞いをする人が増えれば、周りからの反発が起こるのも必然だ。
道徳心が低いままで許されるわけでもないから、人は道徳模範の抑圧から解放されたものの、それぞれが独自に道徳というものを実行していく必要に迫られたわけである。
このようなことは、江戸→明治だけの話ではなく、現在にも残っているのではないかと思う。
江戸時代のそれとは異なるが、「世間」というものがもつ道徳模範という基準への照らし合わせが日々行われている。
この一律の模範があることに日本人は慣れているのだろう。
それの方が確かに楽な面があるのだろうとも思う。
しかし、その模範的な道徳一本の社会対しては、一方で息苦しさがある。
人は、そこから解放されるべく、また、新しい自由の道を模索する。
この動きが明治維新以降ずーっと続いている、と言ってもよいのではないだろうか?
新しい自由の道では、これ見よがしに羽目をはずす人間も出てくる。
現代の調和バランスに鑑みて、批判されたり修正されながら進んでいくのだと思う。
私のマンションの郵便受けのそばに不要なちらしを捨てるためのダンボール箱が用意されていたことがあった。
その中に食べた弁当のプラスチック容器が捨てられ続けたことで、ダンボール箱は撤去されてしまった。
当時はなんとも思わなかったが、撤去されてみるとダンボールが非常に有難かったのだと感じた。
これは小さなことではあるが、まさにこのようなことが道徳と自由の調整の一例でもある。
自由が行きすぎて道徳が損なわれ、以前以上に制約を受け自由が奪われたりもする。
試行錯誤が行われ、道徳と自由とのラインが振り子のように揺らぎながら時間が流れていく。
今もこれからもこのような道徳と自由との調整がずーっと続いていくのだ。
この道徳の話を海外にあてはめてみると、海外には自分の外に宗教(キリスト教、ユダヤ教等)という道徳模範があるのだが、「宗教は死んだ」という哲学者が出てくるなど、こちらでもその道徳心が低下している、と言われたりする。
このことは日本の明治維新以降の現象と同様のように自分の目には映る。
人間はやはり、外に決められた一本の道徳(ルール)がないとうまくやっていけないものなのだろうか?
漱石は文芸の浪漫主義と自然主義、それらと道徳の関係についても語っている。
浪漫主義とは理想の主人公が登場して、憧れるような、見本となるような道徳を見せてくれる文芸。
自然主義とは、理想の人ではなくて、身の回りにいるような不道徳な人も描写するなど、現実を描写した文芸である。
当時は、浪漫主義にこそ道徳がありーそれは主人公の道徳心がみんなのお手本になるからー、自然主義には道徳がない、といった批判があったようだ。
漱石は理想通りにいかない現実にも、共感したり道徳を考察したりすることがあり、そういう意味で自然主義も道徳に寄与するものだと主張している。
更に漱石は、浪漫主義はすでに終わった、とまで主張している。
浪漫主義に描かれる登場人物は、理想であり現実にはいない、フィクションである。
情報の少ない時代には、大衆はそういう人が実際に存在するのだ、と思い込まされて、そうならなければならない、という強制力を持った。
ところが、理想と思える人にも、実際には必ずしもそうではない部分を持ち合わせているのが人と言うもの。
情報がいろいろ回るようになる中で、大衆はそのことをわかってしまった。
そんな理想の人はこの世にいないのだ、と。
漱石は言う。
現実にはない理想をさも現実であるかのように見せる浪漫主義は不誠実である。
不誠実な浪漫主義と少なくても現実を映していてその点においては誠実な自然主義とでは、どちらが道徳的なのか?
漱石のこの言葉が痛快に響く。
そういえば、本や映画の主人公は、昔はと言えば王やリーダーがお決まりだったのだが、時代と共に、名もない兵士だったり、民間人だったりに変化してきている、と聞いたことを思い出した。
王やリーダーの逸話は飽きてきた、というか、どこか胡散臭く感じるようになった自分がいる。
名もなき兵士に、胸打つものがある。
ある哲学者の方が、コロナ禍を経験してこんなことを感じたと言っていた。
「いろいろなものに権威はなくなってはいたが、更に権威の崩壊に拍車がかかった」
いろいろな情報が出回る世の中は、権威喪失が進み、情報は権威喪失を進めるものだ。
この権威喪失は映画の主人公のことと見事にリンクする。
私は、権威喪失が悪いものだとは思っていない。
だからといって国家権力が不要なものなどとは思ってはいない。
権威の喪失を認識した時に、個人は自分が立たないといけなくなる。
権威を喪失した時に、やっと権力者と対等に話せるようになるのだと思う。
自由のために何よりも正直でありたいし、外の決め事に頼るのではなく、個人として立っていたい。
もう一つ紐づいた話がある。
エーリッヒ・フロム「人生と愛」
[itemlink post_id=”8351″]
最近ーとはいってもこの本は1980年頃のものだがー社会の道徳心が低下する中で、若い人に芽生えている新しい道徳心を紹介している。
若い人は、自分自身が理想的な人間ではないことを認めており、不完全な自分を認識している、だから誠実である、というもの。
この誠実さが新しい道徳心であり、この不完全さが本来の人間味であると。
これに対して昭和世代ーそうと言い切っていいのかわからないがーには、理想を求める感覚、そして、理想的であらねばならないという感覚が色濃く残っている。
これは江戸時代の模範道徳、そしてそれを受け継いだ現代の世間の道徳による影響なのだろうと思う。
自分が持っている罪の意識を隠さなければならないという不誠実さであり、自分がよい性格のかたまりであるようにいつも見せかけなければならないという意味の不誠実さである。
この不誠実さはまさに昭和世代の特徴であり、昭和世代の苦しみでもある。
自分の根底に常に理想と現実のギャップを抱えているから、自己肯定感が低くなる。
それをまた虚勢で多い隠す。
昭和以降の世代でもこの価値観を親などに押し付けられて苦しんでいる人もいるのだろう。
エーリッヒ・フロムは日本のことを書いたのではないのだろうが、日本にも同様に当てはまっていると感じる。
私はこの一律の道徳がある社会と多様性を享受する社会というものは、基本的に矛盾するものと考える。
それでも、その両方の落としどころを探求していくべきものだと思っているのではあるが。
私の個人主義
(個人主義とは)党派心がなくて理非がある主義である。
私共は、国家主義でもあり、世界主義でもあり、同時に個人主義でもある。
国家が滅びるか滅びないかという時に、ただ無暗に個性の発展ばかりに目懸けている人はいないはず。
個人主義を推奨する漱石は、「ならば国家はどうでもいいのか?」という批判を受けたのだと思う。
漱石の言う個人主義は個人がバラバラに好き勝手にやって、国なんてどうでもいいという主義ではない。
個人がそれぞれが自分の理非によって、国を考えるのである。
「保守」だ「リベラル」だと争うが、どちらも大切でバランスをどうとるか?タイミングと程度問題につきるのだと言っている。
国家存亡の危機に晒されれば、保守の方向を強くする必要がある。
そうでない場合は、個人や世界に目を向けるのがバランスである。
「保守」と「リベラル」の揺らぎである。
最近、サイレントインベージョンなども言われるようになったが、このような巧妙なやり方も知った上で、現在の日本を国家の危機とみるか?みないか?そこの判断次第なのだと思う。
[itemlink post_id=”8411″]
この漱石の感性は現在でも通用する普遍的なものだと感じる。
面白さがわかってきた
「私の個人主義」は、上記のように夏目漱石の1910年代の講演を集めた本である。
なんと痛快な本なのだろうか?
大変遅ればせながら、夏目漱石の面白さがわかってきた。
やっと自分の興味が漱石に追いついてきたといったところだろうか。
この漱石の社会を上から引いて見る、あるいは、大局を捉える視点。
世の中全体が何かに対していいものだ、などと一方に軸足が乗っているならば、それに水を指すように逆足に重しをかけるような視点。
自己批判も辞さず、社会に対する都合の悪い見方、ネガティブな見方、世の中に忖度せずに、自分に正直で客観的な視点。
漱石は、”気にしい”だったから、自分がある主張をした時に、周りに起こるネガティブな感情や批判は過剰にまで想像できていただろうと思う。
それにもかかわらず、そこから逃げずに、自分に蓋をせずに自分本位を突き通している。
嫌がらせが目的なのではなく、真実を追求したいという思い、あるいは、こう考えねば納得がいかない、という自分が感じた自然な道理に順じようという強い思いを感じる。
これは、いくつもの壁を超え、自分の納得感を貫いたからこそ、シニカルに感じもするし、普遍的なところに通ずるもなのだと感じる。
このことこそが漱石が主張したい個人主義のありようなのではないかとも感じる。
漱石の視点=個人主義の視点は、激流で自分を翻弄し続ける世の中を理解する助けとなる。
1世紀をまたいでも漱石の視点は色あせることがないようだ。
スペイン風邪の前にこの世を去るものの、疫病を人口集中や人口移動による必然だと理解していた漱石。
その漱石はこのコロナ騒動をどう見るだろうか?
人間の無能さと滑稽さを切り取るだろう。
そして、個人主義としての我々の振る舞い方について、シャープなメッセージをしてくれるのだろう。
Photo by Dollar Gill on Unsplash
【著者プロフィール】
RYO SASAKI
私の場合、漱石をここまで痛快に感じられるにはこれだけの時間を要したということなのでしょう。
良い悪いは別にして、自分のアンテナの向きが変わり、変化していることは確認できます。
工学部を卒業後、広告関連企業(2社)に29年在籍。 法人顧客を対象にした事業にて、新規事業の立ち上げから事業の撤退を多数経験する。
現在は自営業の他、NPO法人の運営サポートなどを行っている。
ブログ「日々是湧日」
幅を愉しむwebメディア「RANGER」に対するご意見やご感想、お仕事のご相談など、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。
最後まで読んでくださりありがとうございます。