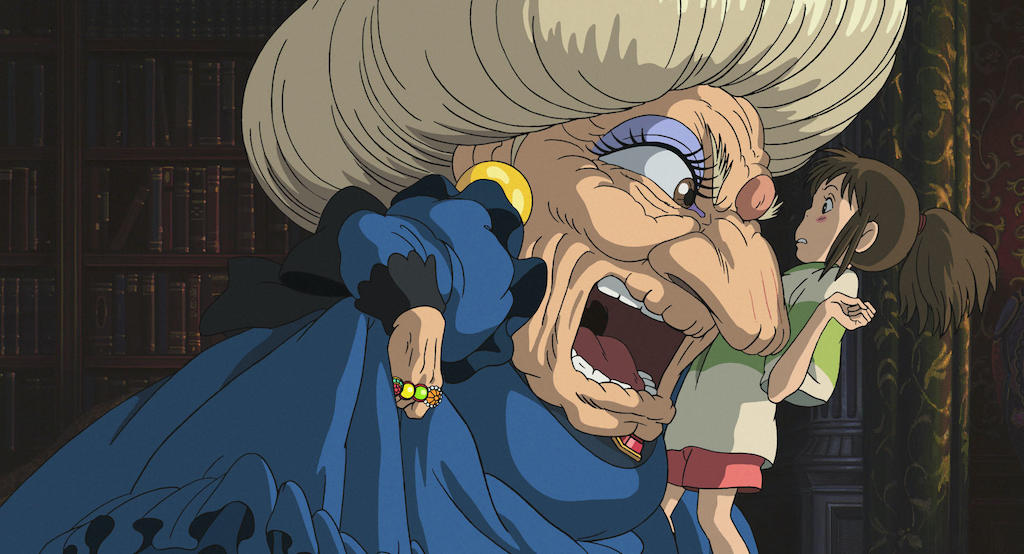天才哲学者マルクス・ガブリエルもやはり同じようなところに至ったようだ。

ドイツの哲学者マルクス・ガブリエル(1980年生まれ)は、史上最年少の29歳でボン大学の教授に着任。
六か国語(ドイツ語、英語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、中国語)を自在に操り、古典語(古代ギリシャ語、ラテン語、聖書ヘブライ語)にも習熟しており、天才哲学者、哲学会のロックスターなどと言われる。
彼の著書で哲学書としては異例のセールスを叩き出した本がこちら。
著書「なぜ世界は存在しないのか」
[itemlink post_id=”8880″]
マルクス・ガブリエルの新実在論
哲学には、実在論と観念論という反対の立場がある。
実在論は、人間の認識や知覚に依存しない事物の客観的実在を認める立場。
観念論は、外界は人間が観念で認めた、仮象の世界にすぎないとする立場。
人は通常、自分が見えているものをすべて事実だと思ってそれに反応しながら生活しているのだが、果たしてその事実が本当なのか?と問われると怪しさがある。
動物などの視界に映っている外界は、人のそれとは異なるわけで、それが人より粗い画像だったとしたら、逆も真なりで、人の画像よりも鮮明な外界がありうる、とも考えられる。
実際に、人には聞こえない周波数を音として捉えられる動物もいる。
これは視覚聴覚だけの話だが見えているものが聞こえているものが、本当の外界である、という自信などはない。
ましてや、この物理的なこと以外の外界の見方については、それぞれの観念であり自分の観念が真実であるとは、とても言えないし、真実がなんなのかもわかりはしない。
例えば、ある花が何色か?などについてのものならばまだしも、世界は幸せなのか?怪我した人は可愛そうなのか?神は存在するのか?などなどの概念的なものになると、更に自信がない。
人は、物事に自分なりの解釈を加えて評価して真実だとして生きているものだ。
これは考え方次第で、見える世界は変わる、とよく言われるものである。
マルクス・ガブリエルの新実在論は、客観的実在もあるし、人は観念で捉えている実在もある、という立場をとっている。
目の前に確かに見えるテーブルをないことにして、そこを通り抜けようとしても、ぶつかって痛いのは人も動物も変わらない。
何色か、ぶつかってどう感じるかは異なれども、ある固体がそこにあるという客観的実在には変わらない。
何かがそこに存在している。
三次元空間としては、ということになるのだろうか。
人が持っている知覚でとらえて(知覚がどこまでの精度なのかによってこれすらも疑うことはできるが)、存在する何かがあることと、それを人が知覚と共にそれになんらかの解釈を付与している(テーブルにぶつかったことを自分は不注意な人間だ、などと評価すること)、ということの両方を説明するのは、実在と観念の両方を認めることでしかない。
そして、観念による「不注意な人間」という意味付けを事実ではないとして切り捨てたところで、社会は機能不全になるように思える。
このことは同時に、社会において、知覚認識に限界がある人間というものが客観的な実在を認識する、ということの難しさを感じる。
そしてそこから、人それぞれの観念の多様性を想像した時に、異なる意味をもつ人と人のすり合わせの難しさも感じる。
社会には、人と人がすり合わなくてもいいことはたくさんあるが、客観的な事実が共通して、すり合わないと不安定になることも存在する。
ニヒリズムに抗して
ニヒリズム(虚無主義)とは、今生きている世界、特に過去および現在における人間の存在には意義、目的、理解できるような真理、本質的な価値などがないと主張する哲学的な立場のこと。
ニヒリズムの代表と言えば、ツルゲーネフ・ニーチェ・カミュなどになる。
マルクス・ガブリエルはニヒリズムに対しては、自然科学だけを重視すると、宇宙の中の太陽系の中の惑星の中の地球の人間なんて、更に言えば70数億人のうちのひとりの自分なんて意味がない、というところに帰結する、と言っている。
自然科学だけに傾倒するとここに至ってしまうから、自然科学だけに傾倒せずに心(精神)の固有の働きをも肯定するものになっている。
心固有の働きとは、情緒であり欲望でもあり、喜怒哀楽を感じること、中でも何でもいいから喜楽を感じること(人間は怒哀を感じないようにはできていないが)に尽きるということなのだと思う。
ここにも感情と理性のバランスがあるのだろうけれど。
この「自分はちっぽけなものなんだ」という認識は、目の前の小さな問題に囚われ、絶望を感じてしまっている時に、そこから解放するために役立つものでもある。
「なんと小さなことで悩んでいたんだろう!世界は広いんだ!」と。
しかし、そのことによって逆に何も意味のない自分、無力な自分に対して絶望を感じてしまうことにもなる。
人という者は、何ともデリケートであり、何ともわがままな存在だとあらためて思う。
極端になりすぎることへの危うさも感じる。
自然科学だけを信奉することは、苦しい人生になり、別のことで折り合いをつけるのがいい、ということには確かに共感する。
これは唯物論と唯心論の対立にも符号するように思える。
無数の意味の場において対象は存在する
マルクス・ガブリエルは、世界には無数の意味の場が存在し、その中に対象が存在している、という。
水というもので説明すると、自然科学という意味の場において、H₂Oとして現象する。
H₂Oという意味が現われる=H₂Oとして存在する、ということである。
砂漠という意味の場では、貴重な飲み物という意味をもち、貴重な飲み物として存在する。
サウナという意味の場では、身体を冷やすものという意味をもち、身体を冷やすものとして存在する。
水という対象を規定する場(意味の場)が最初に存在して、その場においての意味を加えて、水の存在が明確になる。
そして、水が意味をもつ意味の場が無数に存在している。
水(=対象物)は、ある意味の場から人間が眺めることで存在が明確になるものでもあるのだが、一方では、その意味の場から人間が眺めなくても水は存在する。
人間が様々な意味の場から眺めた水の意味だけが、水の存在意義でもなく、他にも存在の意味はある。
この内容に、また、観念論と実在論の両方が現れる。
観念論と実在論はおいておいて、結論は、水というものに普遍的な説明がひとつあるのではなく、無数の意味の場における存在があるということになる。
水というものには、人それぞれの学習や経験から、無数の意味、存在意義があるわけだ。
このことが、水に限らずに、すべての事象に当てはまるということになる。
ある事象についてある説明をした時に、それはわずか一部の意味の場における意味であり、すべてを説明しているものではない。
このことは、人が目指すべき生き方についても、何かひとつの普遍的な正解、あるいは、理想があるわけでもないということにつながることになる。
マルクス・ガブリエルは 人生をどう生きるか?について、最後に以下のように締めくくっている。
人生の意味とは生きることに他なりません。
つまり、つきることのない意味に取り組み続けることです。
なぜだか、いろんなことの目的や意味を知りたい人間がいる。
その人間が生きる意味を問うた時に、意味を問い続けることが意味である、と禅問答のようにして天才から突き放されて終わった。
二項対立の克服
哲学というものには、「理解が難しくて、また、理解できたとしても、日々の生活に活かせない」という印象がぬぐえない。
さてこれらのことから、明日から何にどのように活かしたらよいだろうか?
活かすためのポイントを3点ほど上げてみたい。
①普遍的な答えがないから、多様性の中で折り合いをつけていくこと。
②物事は二項対立を統合して中庸を選択していくこと。
③感情と欲望を結局は大切にするということ。
*
①普遍的正解がないから、多様性の中で折り合いをつけていくこと。
無数の意味の場が重なって存在する中では、答えはひとつではない。
意味の多様性を認識して、折り合いをつけていくことにしか、解決策がないということ。
②物事は二項対立を統合して中庸を選択していくこと。
哲学もそうだが、様々な思想は新しく生まれては、その普遍性の信奉者が現れる。
その一方で、思想の普遍性が批判され、新たな思想に取り替えられる。
この繰り返しがあり、普遍性などというものがないことの証明を意図せずにみんなで続けてきているようにも見える。
普遍性を求めることが、普遍性がないことを証明している。
天才哲学者マルクス・ガブリエルの主張は、実存論と観念論の両方を是としており、その二項対立の統合というか、中庸やアウフヘーベンを結果的に踏襲したものになっていると感じる。
統合された二項対立は、
実在論と観念論
普遍性と特殊性
※この対義語は何か不十分な気がする。
唯物論と唯心論
科学 ⇔ 宗教
科学 ⇔ 迷信
科学的 ⇔ 感覚的
科学的 ⇔ 非科学的
※科学の反対語を探してみたらピッタリするものがなかった。
無理くり上げてみると、上記のようなものになる。
この科学に対して二項対立する対義語が立ちきれていないところに、この世の中の認識の偏りを感じる。
この二項対立の統合については、以前に極への偏りの問題と中庸の大切さを書いた記事にも共通するものだ。
参照:人生はカウンターを当ててずーっと「揺らいでいく」のがいい。
ルドルフ・シュタイナーは、この二項対立について以下のようなことを言っている。
「人生を理解するということは対立の中に魂のすべてで立つことである。
生命そのものは、絶えざる対立の克服であり、また新しい対立の創造であるのだから。」
参照:書籍「ルドルフ・シュタイナーの100冊のノート」2002年6月発行
ここでいう「対立の克服」も「対立の創造」も「複数の意味の場」から起こる現象である、ということにつながってくる。
③感情と欲望を結局は大切にするということ。
人間として生まれたのだから、自然科学などの観念に縛られずに人間らしく生きる、ということ。
その人間らしさには、感情と欲望が不可欠である。
最近読んだいくつかの本から得られた結論も、どうもここに至っている。
最後に、今回は新進気鋭の天才哲学者の思想が、他の偉人たちの思想、そしてそれに共感した自分の感覚ともつながって、新年早々にとりあえず安心した。
P.S.
紅白歌合戦の視聴率が低迷したことについてのニュースを見ていると面白いものがありました。
「年末年始の日本人は、『紅白』を見て年越しそばを食べ、除夜の鐘を聞いて、初詣に行き、お節料理をつまみつつ一盃やって、お雑煮も食べるわけです。美しき様式美と言っては言い過ぎかもしれませんが、偉大なる茶番、もしくは型を楽しんでいるわけです。そんな中、テレビ番組だけが変化しても、お茶の間では受け入れられません。」
コア視聴率を意識して、若者向けにしたことが低視聴率の原因だとする記事。
私は、この「美しき様式美」「偉大なる茶番」という言葉が印象的でした。
このような過ごし方をしている家がどのくらい存在しているのだろうか?
それはどのくらいでもいいとして、このような過ごし方は「恒例の幸せ」とも「様式美」とも「茶番」とも意味づけができるわけで、そこに正解などなくて複数の意味、存在があること、そして何らかの力学によって折り合いをつけて、家族の過ごし方が決定されているであろうということに思いを馳せました。
これが、新実在論の卑近な一例なのだ、と感じた次第で、何でも納得できる意味付けをして人生を歩むにつきるということでしょうか。
<参考図書>
[itemlink post_id=”8881″]
Photo by Dan DeAlmeida on Unsplash
【著者プロフィール】
RYO SASAKI
どんな意味づけをしてどんな年末年始を過ごしたのでしょうか?
私は少し高いおせちと少し高いお酒を奮発して買った以外は、起床時間も就寝時間も含めて、行動自体はいつもとあまり変わらぬ年末年始でした。
それでも、気持ちはいつもと違って少し盛り上がった感覚がありました。
工学部を卒業後、広告関連企業(2社)に29年在籍。 法人顧客を対象にした事業にて、新規事業の立ち上げから事業の撤退を多数経験する。
現在は自営業の他、NPO法人の運営サポートなどを行っている。
ブログ「日々是湧日」
幅を愉しむwebメディア「RANGER」に対するご意見やご感想、お仕事のご相談など、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。
最後まで読んでくださりありがとうございます。
これからもRANGERをどうぞご贔屓に。