もしかすると「あらゆる人種の中で現在を生きていない人の割合が多いのは日本人」と言えるのかもしれない。
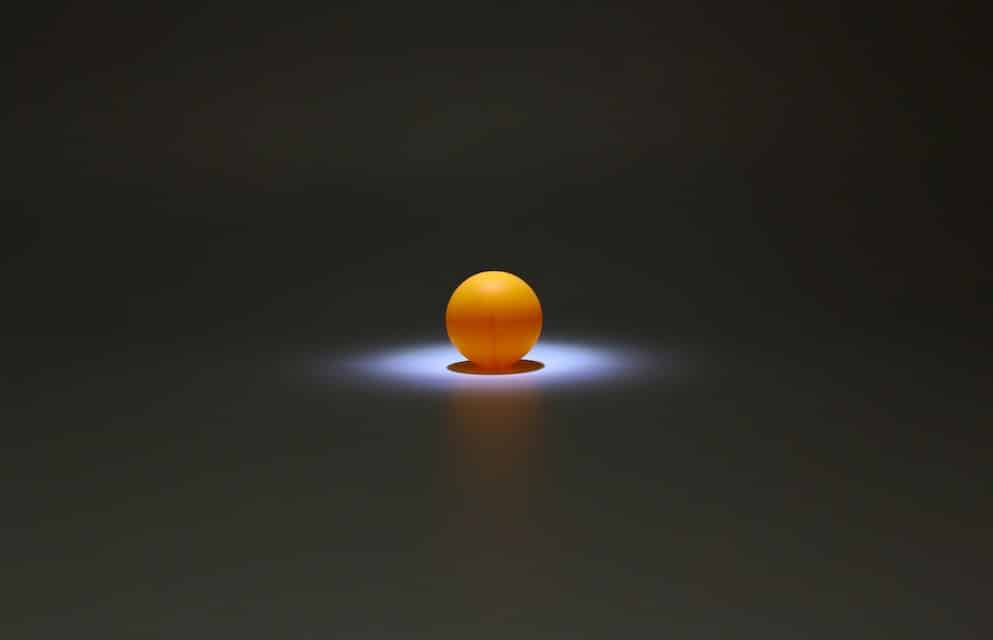
最近、久々に読み返していたweb記事の中でハッとする箇所がありました。
読み返していたのは2018年のログミーの記事。
人間の「集中」について関心を寄せていた当時の自分に刺さりevernoteにストックしていたものです。
当時から変わらず今の私も集中については引き続き関心は高く、ここでふと読み返してみました。
平日で一番集中できるのは「水曜日」JINS MEMEでわかった“集中して働ける環境”
そして今回再読している中で、ハッとした瞬間は以下の箇所を読んだ時に訪れました。
日本人はとくにですが、日本人はセロトニン・トランスポーターという遺伝子が他の人種と違っていて、不安を感じやすいんです。
あらゆる人種の中で一番不安を感じるのは日本人なんですね。
なので一番東まで逃げてきたという背景があるんです。
それで、不安を感じるとどういうことが起きるかと言うと、「あの人はどう思っているだろう?」「空気を読め」「誰かがなにかを怒っているんじゃないか」というように、“気にしい”なので、“気にしい”の人は集中ができないんですよ。
なぜハッとしたかと言えば、私の中で以下の知見と結びついたからです。
不安は先のこと(未来)を考えるから生まれる。
どのように結びついたのかは以下の通り。
あらゆる人種の中で日本人は一番不安を感じる
↓
不安を感じるのは先のことや未来のことばかりを考えるから生まれる
↓
ということは、あらゆる人種の中で日本人が一番未来のことを考えている割合が多く、すなわち現在を生きていない人の割合も多いと言えるのではないか?
といった具合です。
以降で順を追って補足をしていきたいと思います。
*
「あらゆる人種の中で日本人は不安を感じやすい」
これに関しては、前述の記事以外のところでも確認したことがあり「きっとそうなのだろう」という見解です。
私は外国人との接点が少ないため(ゼロではない)、そことの対比はそれほど参考にはできないのだが少ないサンプルでも感じるところはあります。
昔「日本人は胃腸が弱い」という歌が流行った時がありました。
これはどうやら本当らしく、日本人は民族的に胃腸が弱い。
しかも、その弱さは世界有数。
長野の百草丸、伊勢の萬金丹など伝統薬の中に胃腸薬が多いのは、日本人が遺伝的に胃腸が弱く、胃腸の力を回復することが全身の健康に役立つとしてきた何よりの証拠と言えるでしょう。
思うに、この「胃腸の弱さ」が「不安を感じやすい」ところにも繋がっているのではないでしょうか。
胃腸は「第二の脳」という主張を聞いたことがある人もきっと多いはずです。
*
さて、そんな「不安」という感情はどのようにして私たちの中に生まれてくるのでしょうか?
昨年末「グッドバイブス ご機嫌な仕事」の著者として知られる倉園佳三さんが主催するオンラインイベントに参加した際、ご本人の口から以下のようなことを聞きました。
不安は先のことを考えるから生じる。
先のことを考えなければ生じにくくなる。
本も改めて読んでみると以下の記述を見つけることができました。
すべての不安は未来から生まれる
この倉園佳三さんがおっしゃる「未来(先のことを考える)から不安になる」という不安の発生メカニズムについては、自分の実体験からも腹にしっかり落ちました。
それもあって現在では私の確信の一つとなっています。
具体的には、
300段もある神社の階段を上まで見てしまうと「果たして自分は登れるのだろうか」「絶対大変だ」といった不安が生じる。
あるプロジェクトの計画を立てられた時に実行する必要のあるタスクを束ねてみると「こんなにタスクがあったら終わるのか分からない」「無理かもしれない」といった不安が生じる。
きっと誰しも思い当たることはあるでしょう。
しかしいずれにしても、未来、先のことを考えなければ不安は生じなくなる。
300段もある階段の上をみる事なく、目の前にある階段を一つ登ることだけに集中すれば前述のような不安は出てこない。
先の計画を常に捉え逆算することなく、目の前にあるこのタスクだけやればいいということで集中して取り組めば前述のような不安は出てこない。
つまり言い方を変えると、未来、先のことを考えなくすれば不安は今この瞬間に消すことができるということです。
*
不安が生じる原因は未来にある。
そして、あらゆる人種の中で日本人は一番不安を感じる。
この二つをあわせて考えていくと思うに、日本人はあらゆる人種の中で一番「未来のことを考えている」という理屈が成り立ちます。
そして、未来のことを考えている最中というのは当然ながら「現在」に意識はありません。
ゆえに、もしかすると「あらゆる人種の中で現在を生きていない人の割合が多いのは日本人」と言えるのかもしれない。
冒頭の記事を端にして以上のようなことを考えました。
また、そんな日本人にこそ「現在に集中すること」に効果があり、マインドフルネス的な行為も効くのだろうという思いにも至ります。
人によっては飛躍した理屈に聞こえたかもしれませんが、私にとっては大きな気づきだったので書き残しておきました。
引き続き自分が関心のあるテーマとして探求していきたいです。
UnsplashのWilhelm Gunkelが撮影した写真
【著者プロフィールと一言】
著者:田中 新吾
昔は不安は必ずあるものでそれを軽くすることはできると思っていましたが、今ではこの考えもアップデートされています。
プロジェクト推進支援のハグルマニ代表。 お客様のプロジェクトの推進に必要とされる良き「歯車」になるがミッション。 現在は、大企業様、中小企業様、NPO法人様など複数のプロジェクトの歯車になっています。 ネーミング、習慣、コミュニティ、地域づくり、タスクシュート、白湯、情報化、情報処理が探求と実践の領域。
●X(旧Twitter)田中新吾
●note 田中新吾
会員登録していただいた方に、毎週金曜日にメールマガジン(無料)をお届けしております。
「今週のコラム」など「メールマガジン限定のコンテンツ」もありますのでぜひご登録ください。
▶︎過去のコラム例
・週に1回の長距離走ではなく、毎日短い距離を走ることにある利点
・昔の時間の使い方を再利用できる場合、時間の質を大きく変えることができる
・医師・中村哲先生の命日に思い返した「座右の銘」について
メールマガジンの登録はコチラから。
最後まで読んでくださりありがとうございます。
これからもRANGERをどうぞご贔屓に。











コメントを残す